接骨院・鍼灸院の広告規制ガイド|2025年版 最新ルールと対策法
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
接骨院・鍼灸院の広告規制とは?2025年の最新動向

広告規制の法律的根拠(柔道整復師法・あはき法・医療法)
接骨院や鍼灸院が広告を行う際には、いくつかの法律が深く関係しています。最も中心となるのは柔道整復師法と**あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律(通称:あはき法)**です。これらの法律では、施術所や施術者が広告で表示できる内容が厳格に限定されています。
例えば、広告で掲載できる項目として認められているのは以下のような基本的な情報に限られます。
- 施術者の氏名
- 施術所の名称および住所・電話番号
- 施術日または施術時間
- 厚生労働大臣が指定するその他の事項(例:予約の有無、休日・夜間施術、訪問施術の有無、駐車場の有無 など)
一方で、「腰痛が必ず治る」「わずか3回で改善」など効果を断定する表現や、「専門家による特別療法」など科学的根拠が乏しい施術内容のアピールは広告規制の対象となります。
さらに、医療法も関連し、医療機関ではない接骨院・鍼灸院が「治療」「診療」といった医療行為を想起させる表現を使用することも禁止されています。
また、景品表示法では過大な宣伝や虚偽表示を防ぐため、料金やキャンペーンの表現にも注意が必要です。たとえば「期間限定!初回半額」「驚異の90%改善率」といった広告は、患者に誤解を与える可能性が高く、違反につながる恐れがあります。
これらの法律は、患者が誤った情報で施術所を選び、不利益を被らないようにするためのものです。つまり、広告規制は患者保護の観点から存在し、結果的には施術所の信頼を守る役割を担っています。
広告とみなされる条件(誘引性・特定性・認知性)
広告かどうかの判断は感覚的に難しい場合があります。法律では、誘引性・特定性・認知性という3つの条件のすべてを満たしたものを広告としています。
- 誘引性
患者を呼び込む意図があるかどうかです。たとえば、「痛みが即日改善」や「初回無料体験」など、患者に来院を促す要素があれば誘引性があると判断されます。 - 特定性
施術者や施術所を特定できるかどうかです。住所や電話番号、院名、公式サイトのURLが載っていると特定性が認められます。 - 認知性
誰でも見ることができる状態かどうかです。インターネット上に公開された広告、新聞折込チラシ、屋外看板などは一般に広く認知できるため広告に該当します。
例えば、患者に直接手渡す案内パンフレットや院内での料金表掲示は広告に当たらない場合もありますが、不特定多数が閲覧できる状態になると広告とみなされる可能性があります。この違いを正しく理解することが重要です。
広告に記載できる内容と禁止される内容
接骨院や鍼灸院が広告に記載できるのは、主に以下の項目です。
- 施術者の名前(柔道整復師・はり師・きゅう師など国家資格名を含む)
- 施術所の名称、住所、電話番号
- 施術日、施術時間
- 予約可否や出張施術の有無、休日・夜間対応の有無
- 駐車場に関する情報
一方で、禁止されている表現は以下のようなものです。
- 効果を断定する表現(「必ず治る」「どんな症状でも改善」など)
- 具体的な施術内容や特殊手技の詳細な説明(「独自の電気療法で驚きの効果」など)
- 実績や経歴の過度な強調(「施術件数3万人突破」「20年の経験による完璧な手技」など)
- ビフォーアフター写真や患者体験談の掲載
これらが禁止されている理由は、患者が広告を見て誤解を抱き、不適切な施術を受けるリスクを減らすためです。
接骨院・鍼灸院の広告で違反しやすい表現と注意点

効果を断定する表現のリスク
広告で最も違反しやすいのが、効果を断定する表現です。
例えば、「腰痛が必ず治る」「1回で効果を実感」といった表現は、患者に確実な改善を保証していると誤解させます。実際、こうした表現を使用した結果、保健所の調査を受け、広告削除を指導された院もあります。
患者ごとに症状や回復速度は異なります。広告では「改善が期待できます」や「症状に合わせた施術を行います」といった期待値ベースの表現にとどめることが安全です。
無資格者を想起させる表現
スタッフ紹介で多いのが、「専門スタッフ在籍」という表現です。
一見問題なさそうですが、これだけでは国家資格を持たない人が施術している印象を与える恐れがあります。たとえ無資格者が施術に関わっていなくても、誤解を招いた時点で広告違反に該当するリスクがあります。
スタッフ紹介をする場合は、資格の有無を明記することが必須です。例えば、「柔道整復師資格保有の院長が対応」「施術はすべて国家資格者が行います」といった表現にすると誤解を防げます。
料金・経歴・施術内容に関する注意点
料金の表示に関する規制
広告に料金を記載することは原則認められていません。「初回限定1,980円」「キャンペーン実施中」といった記載は典型的な違反例です。
料金を示す場合は、院内掲示や予約時の直接説明といった方法を選ぶのが安全です。
施術者の経歴・実績に関する規制
「施術経験20年」「施術件数3万人超え」などの経歴や実績を強調する広告も禁止対象です。資格そのもの(柔道整復師、はり師、きゅう師等)の記載は可能ですが、患者を誘導する目的で経歴を誇張する表現は避ける必要があります。
ビフォーアフター写真・体験談の取り扱い
施術前後の写真や患者の体験談は、効果を保証していると受け取られかねません。たとえば、「一度の施術で腰がまっすぐに!」という広告は、結果を保証する印象を与え、違反になる可能性があります。写真を使う場合は院内の雰囲気や施術室の清潔感を伝える程度にとどめましょう。
2025年版 広告ガイドライン改正のポイント
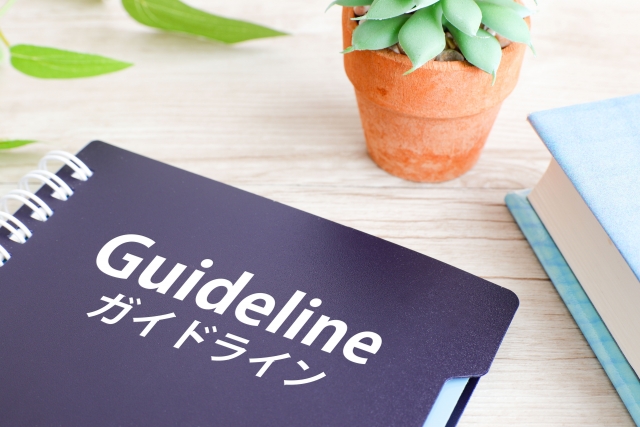
改正の背景と目的
今回の改正は、SNSやウェブ広告の急速な普及を受けて行われました。以前は紙媒体が中心でしたが、InstagramやYouTubeを使って集客する施術所が増加しています。その結果、誇張表現や誤解を招く表現がネット上で拡散されるケースも増えました。
このような状況に対応するため、ガイドラインは広告と認められる条件の明確化と禁止事項の追加を目的に改正されています。
新たに追加された禁止事項
改正では、特に科学的根拠のない施術方法の強調や体験談の過度な利用が禁止されました。
例えば、「独自の手技でどんな症状も改善可能」「体験者全員が効果を実感!」といった広告は違反対象です。また、SNSに患者の顔や身体の一部が特定できる写真や動画を載せることも制限されます。
SNSやインターネット広告における対応
SNSや動画広告は拡散力が強いため、誤解を招きやすい特徴があります。特にビフォーアフター動画や患者インタビューは、見る人に過度な期待を持たせるリスクがあります。
改正後は、SNSで情報発信する際も、法令に沿った表現チェックリストを活用する体制が求められます。
違反するとどうなる?罰則と行政指導の実態

行政指導・改善命令の流れ
広告違反が疑われると、まずは保健所や地方厚生局の指導が入ります。初回は改善を求める指導にとどまりますが、従わなければ改善命令に進みます。改善しないまま放置すると、最終的に告発や裁判沙汰になる可能性もあります。
罰則(30万円以下の罰金)と免許停止リスク
柔道整復師法第30条では、広告規制に違反した場合、30万円以下の罰金が科されます。悪質な場合は業務停止命令や免許取り消しになることもあります。過去には、繰り返し違反した施術所が業務停止処分を受けた事例も報告されています。
過去の事例から学ぶ広告違反の教訓
「必ず治る」と広告に書いていた接骨院が罰則を受けたケースや、SNSで患者写真を無断掲載して指導を受けたケースがあります。広告規制を知らなかったでは済まされないのが現実です。
広告規制に対応した効果的な集客方法
広告規制を遵守しながらできる施策
広告規制があるからといって、集客を諦める必要はありません。診療時間、場所、予約方法など、基本情報を正確に伝えるだけでも患者にとっては重要な情報です。さらに、施術理念や院内の雰囲気を写真で伝えることも、誠実な集客につながります。
ホームページ・院内掲示物の活用
ホームページは自由度が比較的高く、理念や施術方針を詳しく紹介できます。写真や動画で院内の様子を伝え、清潔感や信頼性を印象付けることが可能です。料金体系や施術内容の詳細説明は院内掲示物で補完し、外部広告に頼らず院内完結型の情報提供を目指しましょう。
口コミ・地域連携による集客強化
口コミは、広告規制に影響されない強力な集客手段です。高品質な施術を継続することで自然に口コミが広がります。さらに、地域イベントへの参加や異業種とのコラボレーションなど、地域に根差した活動は信頼獲得にもつながります。
まとめ:広告規制を守りながら成功するために
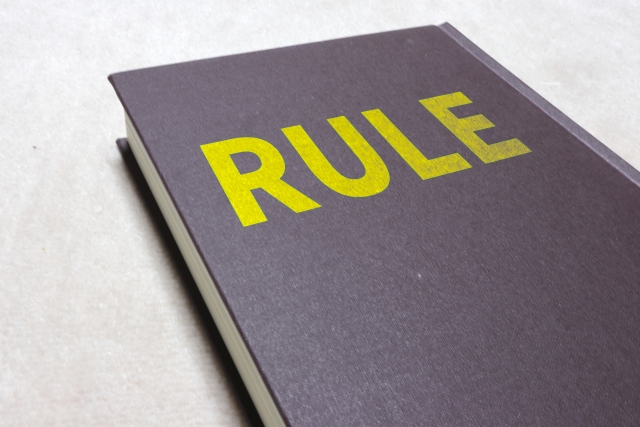
法令遵守が信頼につながる理由
広告を法律に沿って行うことは、患者にとって安心感を与えます。短期的な集客効果を狙って規制を無視すると、かえって信頼を失いかねません。誠実で正しい情報発信こそが長期的な経営成功の基盤です。
今後の広告戦略に必要な考え方
これからは広告規制を前提に、口コミ、地域連携、オンラインでの誠実な情報発信を組み合わせることが重要です。法律を理解し、誠実な集客を行うことで、安定した経営と地域からの信頼を両立できます。



