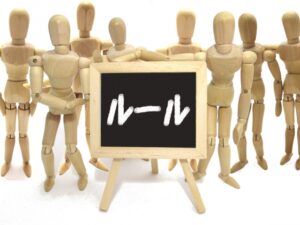接骨院・鍼灸院の利用率は低い?意外と知らない現状と課題
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
接骨院・鍼灸院の利用率は本当に低い?最新データで見る現状

インターネットで検索すると、リサーチ会社等により誤差はありますが、接骨院・鍼灸院の利用率は、全国平均でおよそ14.5%前後にとどまり、前年からは1.5ポイント下落しています。1年以内に利用した人に絞っても16.1%で、潜在需要の大きさに比べると決して高い水準ではありません。街中で院の数は増えているのに、実際の来院者は伸び悩む――このギャップこそが経営の難所です。調査手法や対象の違いにより数字は多少ぶれますが、「思ったより利用されていない」という事実は一貫しています。まずは現状のサイズを冷静に把握し、限られた利用者の中で“選ばれる理由”を設計することが、次の一手につながります。
全国平均の利用率とその推移
直近の指標では、通院経験者の比率は14.5%、直近1年の利用は16.1%という結果が出ています。特に注目すべきは、全体の利用率が下向きに振れている点です。供給サイドの増加や情報過多の中で、患者は「行く必然性」を見失いがちになり、比較検討の段階で脱落するケースが増えています。一方で、20代は20.4%と比較的高い利用が見られ、年代によって需要の山と谷がはっきりしてきました。経営判断としては、全体平均に引きずられず、院の商圏とペルソナに合った「局所最適の指標」を持つことが重要です。例えば、自院の来院率・再来率・紹介比率を定点観測し、地域の人口構成と照らすだけでも、投資配分は変わります。
保険適用外施術の割合と利用動向
利用者の約7割は、保険適用外の施術を受けた経験があります。これは価格感度が高いだけの市場ではなく、「納得できる価値」さえ提示できれば自費でも受け入れられる余地が広いことを示します。反面、価値の伝え方が曖昧だと、費用対効果への不安が増し、受診自体が先送りされやすい。つまり、低利用率の背景には“需要不足”よりも“価値訴求の不足”が潜んでいます。メニュー名や効果説明を患者目線に置き換え、期待できる変化や所要回数、リスクと限界までを丁寧に可視化するほど、初診の心理ハードルは下がります。価格は最後の論点であり、最初の離脱要因ではありません。
年代別に見る接骨院・鍼灸院の利用率の特徴

接骨院・鍼灸院の利用は全世代で一律ではなく、年齢層ごとに傾向が異なります。経営者がこれを理解していないと、どの層にどのようなサービスを訴求すべきかが見えづらくなります。ここでは、各年代の利用率や利用動機の違いを整理し、ターゲット選定や施策立案のヒントを探ります。
20代の高い利用率とその背景
20代は年間利用率が約20.4%と突出しています。美容やスタイル維持に関する意識が高く、SNSや口コミで得た情報を頼りに「新しい施術」を試す行動が目立ちます。施術の効果だけでなく「映える」「自分に合う」などの感覚的価値が重視されるため、柔らかいメッセージやビジュアル訴求が有効です。経営者にとっては、学生・新社会人・スポーツ愛好者など細かいペルソナを描くことで、より的確なキャンペーンを打ちやすくなります。
30代・40代の利用傾向と特徴
30代は仕事や子育てで忙しい層が多く、特に女性は「慢性的な疲れや不調の解消」を目的に来院する傾向があります。40代も同様に健康維持や痛みの緩和が主目的ですが、価格や通いやすさも重視されるため、予約の柔軟性や時短メニューが差別化ポイントになります。施術内容を“目的別パッケージ”として提示すると、限られた時間でも成果を感じやすく、再来率向上にもつながります。
50代以上の低利用率とその理由
50代以上は健康意識が高い一方、接骨院・鍼灸院に対するイメージが「若い人向け」「症状が重い人向け」に偏っている場合があります。結果的に自己流のケアや整形外科・整骨以外の医療機関を選ぶことが多く、利用率は若い層に比べ低めです。経営者がこの層を取り込むには、「予防・未病」「安心感」「長期サポート」といったキーワードで再定義し、施術のハードルを下げることが鍵になります。説明会や無料体験、家族連れでの来院促進なども効果的です。
なぜ接骨院・鍼灸院の利用率が低いのか?主な要因と背景

接骨院・鍼灸院の利用率が思うように伸びない背景には、複数の要因が絡んでいます。単に需要がないのではなく、提供側の情報発信やサービス設計が利用者心理に響いていないケースも多いのです。ここでは経営者視点で、利用率低迷の主な理由を整理します。
認知度不足と誤解
鍼灸や接骨施術の効果・目的が一般に十分理解されていないため、「どんなときに行けばいいのか分からない」という声が根強くあります。結果として、肩こりや腰痛などの軽い不調は自己流ケアで済ませる人が多く、来院につながりません。経営者は、院のホームページやSNS、地域紙などを通じて「どんな悩みに応えられるか」を繰り返し伝え、誤解を解くことが必要です。
施術スキルや効果の見えにくさ
施術の質にばらつきがあると、患者が期待する成果が得られず、口コミが伸びにくくなります。また、効果があっても可視化されていない場合、患者は実感しにくいまま離脱することがあります。経営者は、症状の変化を測定・記録し、分かりやすく提示する工夫をすることで信頼性を高められます。写真・姿勢チェック・数値など簡単な方法でも「見える化」が可能です。
リピーター不足と治癒見通しの不明確さ
初回の来院で満足しても、次回の予約につながらないケースは少なくありません。その背景には「何回通えばよいのか」「どのような改善が期待できるのか」の説明不足があります。治療計画の目安やゴールイメージを提示することで、患者は施術の必要性を理解しやすくなり、継続率も上がります。経営者は施術後に一言添えるだけでも印象が変わることを意識するとよいでしょう。
都市部での競争激化
都市部では院の数が急増し、患者は多数の選択肢の中から選ぶことになります。料金や施術内容だけでは差別化が難しく、「どこも同じ」という印象を与えがちです。経営者は立地や広告よりも、まず自院の強みや専門性を明確に打ち出すことが重要です。例えばスポーツ外傷、女性特有の不調、リハビリなど特定分野に特化することで、選ばれる理由を作りやすくなります。
経営者が押さえるべき課題と改善ポイント

利用率が低いという現実を踏まえたうえで、経営者が取り組むべき課題は「ターゲットの明確化」「信頼構築」「認知度向上」の三本柱です。単に施術内容を充実させるだけでは足りず、来院までの心理的ハードルを減らし、選ばれる理由を可視化する必要があります。
ターゲット層に合わせたサービス設計
年代別に利用目的が異なることを把握し、自院の強みを活かしたメニューづくりを行うことが第一歩です。例えば20代には美容やパフォーマンス向上を訴求し、30代・40代には時短や健康維持、50代以上には予防やリハビリ重視といったように、ペルソナごとのメッセージを設計するだけで反応が変わります。
信頼構築とリピーター獲得の仕組み
一度来院した人に「ここなら任せられる」と感じてもらう仕組みを整えることが、安定経営の鍵です。初回カウンセリングで症状と目標を共有し、改善プロセスを明示するだけでも継続率が向上します。また、フォローアップの連絡やホームケアの提案など、施術外での接点を増やすことが信頼感を育みます。
認知度を高めるための情報発信
「自院が何をしているか」を知ってもらう努力を怠ると、潜在的な利用希望者は他院に流れます。ホームページ・SNS・地域紙・チラシなど、複数の媒体を使って実績や患者の声を発信することが重要です。特に保険適用外施術や専門メニューは、その価値をわかりやすく伝えることで初診へのハードルを下げられます。
低利用率をチャンスに変える!集客・マーケティング戦略のヒント
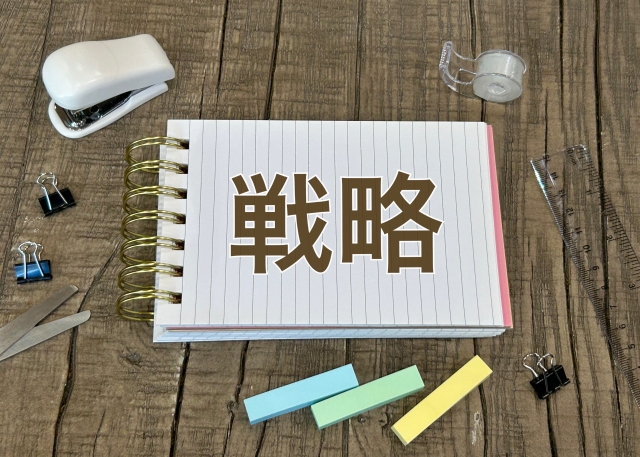
全国平均14.5%という利用率は一見厳しい数字に見えますが、裏を返せば“まだ9割近くの潜在顧客が存在する”とも言えます。経営者にとっては、低利用率を嘆くのではなく、未開拓市場として捉える視点が重要です。ここでは、そのチャンスを具体的な戦略に落とし込むヒントを紹介します。
年代別ニーズを踏まえた施策例
20代にはSNS広告やビジュアル重視のメニュー案内、30代・40代には時短や仕事帰りに立ち寄れる営業時間、50代以上には健康維持や安心感を打ち出したセミナーや体験会など、世代ごとの特徴に応じた集客施策が有効です。特定の層に合わせて施策をカスタマイズすることで、広告費を抑えつつ反応率を高められます。
データを活用した差別化・ブランディング
自院の来院率やリピート率、問い合わせ経路などを記録・分析し、どの層がどんな理由で来ているのかを把握することで、強みと弱みが明確になります。そのデータを基にメニューを見直し、院の専門性を打ち出すことで「この悩みならここ」というブランドイメージを構築できます。さらに、患者の声や事例を許可の上で公開することは、信頼性を高める有効な手段です。