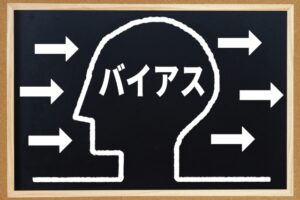経営数字が苦手でもできる!接骨院の収支改善の基本
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
経営数字が苦手な接骨院経営者がまず押さえるべき収支改善の基本

接骨院経営で数字管理が重要な理由
日々の施術が忙しいと、数字は後回しになりがちです。しかし、売上と経費の流れが見えないままでは、どれだけ働いても利益が残りにくくなります。数字は難解な専門用語ではなく、院の現在地を示す地図のようなものです。客数や平均単価、家賃や人件費といった基本の指標が分かるだけで、広告の打ち方やメニュー構成、スタッフのシフトまで判断がぶれにくくなります。結果として、無駄な出費を抑え、注力すべき施術や時間帯に資源を集中できるようになります。まずは「今いくら入り、いくら出ているのか」を正確に知るところから始めましょう。
数字が苦手でも理解できる!収支改善の3ステップ
数字に強くなくても進められる道筋があります。大切なのは完璧さよりも、手を動かして小さく回すことです。次の三つを順番に行うだけで、院の収支は着実に整い始めます。
売上・経費の現状把握
直近1か月分のデータを集め、紙でも表計算でも構いませんので一枚にまとめます。売上は保険と自費を分け、来院数と平均単価も併記すると全体像がつかみやすくなります。経費は家賃や人件費などの固定費と、消耗品や広告費などの変動費に分けて合計します。予約台帳やレセプト、会計アプリの数字をそのまま写すだけでも十分です。細部に迷ったら「まず概算」を優先し、後から精度を上げると負担が軽くなります。
改善ポイントの洗い出し
一枚表を眺めると、手を付けやすい箇所が自然と浮かびます。空き枠が多い曜日や時間帯があるなら集客の施策をそこに寄せます。自費の比率が低いなら、初回後の提案や回数券の設計を見直します。広告費の使い先が分散している場合は、反応が弱い媒体を止めて、反応が出た媒体に集中する判断がしやすくなります。考え方はシンプルで構いません。やめるもの、減らすもの、増やすものの三つに仕分けするだけで、次の行動が明確になります。
実行と検証のサイクル化
決めた施策は小さく始め、1~2週間単位で結果を確かめます。チェックするのは来院数、平均単価、リピート率、粗利の四つで十分です。数字の上下を見ながら、効果が出たものは続け、弱いものは切り替えます。院内で共有し、受付や施術者が同じ目標を見られるようにすると加速します。完璧な計画より、早い検証が収支を押し上げます。続けるほど判断が速くなり、現金残高にも安定感が生まれます。
売上・経費の「見える化」で経営状況を正確に把握する方法
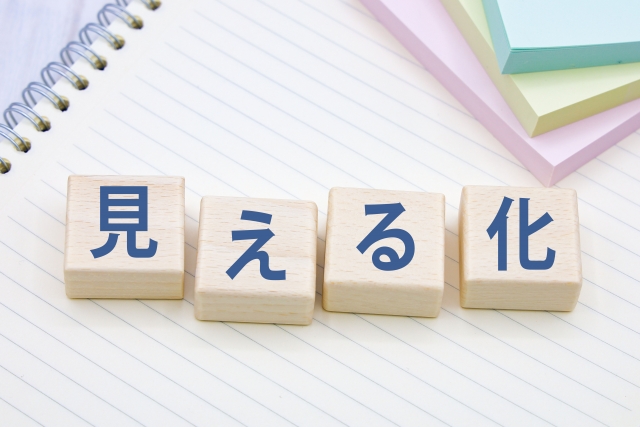
売上データを簡単に管理するツールや方法
売上を正確に把握することは、接骨院経営の第一歩です。紙のノートでも構いませんが、表計算ソフトや無料の会計アプリを使うと、自動で合計やグラフ化ができ、視覚的に把握しやすくなります。保険施術と自費施術を分けて記録し、日ごとの来院人数や平均単価も一緒に入力しておくと、どのメニューが収益の柱になっているかが見えてきます。数字が苦手でも、色分けやグラフ表示を使えば「どこに強みがあるか」「どこに改善余地があるか」が一目で分かるようになります。
経費を分類・整理して把握するコツ
経費は「固定費」と「変動費」に分けるだけで理解しやすくなります。固定費は家賃やリース料、人件費など毎月一定の支出、変動費は消耗品や広告費など月によって増減する支出です。この2つを分けて表にしておくと、どの支出が削減できるか、または効率化できるかがすぐに分かります。支払先や支払日も一緒に管理すれば、資金繰りの不安も軽くなります。
見える化で気づく改善ポイントとは
売上と経費を並べて見ると、思いがけない発見があります。たとえば広告費をかけているのに来院数が増えていない媒体がある、消耗品の発注が重複しているなど、日々の業務では見過ごしていた無駄に気づけます。こうした小さな改善の積み重ねが、最終的に大きな利益改善につながります。数字に強くなる必要はなく、見える化して「気づく」ことが最大のポイントです。
コスト管理で利益を守る!無駄を省くポイント

固定費・変動費を見直す重要性
接骨院の経費には、毎月一定の額がかかる家賃やリース代、人件費などの固定費と、仕入れや広告費、備品など変動する支出があります。まずはこの二つを分けて一覧にすると、どこにお金が流れているのかが明確になります。固定費はすぐに削減しにくいと思われがちですが、契約条件の見直しや使っていないサービスの解約など、意外なところに改善余地が潜んでいます。変動費は月ごとの上下が大きいので、定期的にチェックして必要のない出費を早めに止めることが利益を守る近道です。
仕入れ・備品・光熱費など日常コスト削減のヒント
日常の小さなコストも積み重なれば大きな負担になります。たとえば備品や消耗品の発注先を一本化しまとめ買いをすれば、単価が下がるだけでなく発注業務の手間も減らせます。光熱費も使用量を見える化し、営業時間や設備の稼働時間を調整するだけで削減できる場合があります。また、業務の一部をデジタル化し紙や印刷物を減らすことも効果的です。これらは一度見直すだけで継続的な節約につながります。
コスト削減とサービス品質の両立方法
単に経費を減らすだけでは、患者さんの満足度が下がる恐れがあります。削減の対象を決めるときは、「患者さんに直接影響するもの」と「院の裏側で使われているもの」を分け、後者から優先的に見直します。例えば宣伝のやり方を紙媒体からSNSに切り替える、備品を品質は変えずに仕入れ先を変える、業務フローを見直して時間を短縮するなど、品質を維持しながらコストを抑える工夫が大切です。こうした工夫はスタッフの負担も減らし、結果的にサービス向上にもつながります。
利益率向上のための自費施術・単価アップ戦略

自費施術導入のメリットと注意点
接骨院経営を安定させるには、保険診療に依存せず自費施術を取り入れることが有効です。自費施術は自由に価格を設定できるため、施術の質やサービスに応じた収益が見込めます。また、新しい機器や技術を導入しやすくなり、他院との差別化にもつながります。ただし、いきなり高額なメニューを追加すると患者さんの抵抗感が大きくなることがあります。導入時には説明を丁寧に行い、既存の施術にオプションをつけるなど段階的に移行することでスムーズに定着させることが大切です。
価格設定とメニュー設計の基本
価格を決めるときは、単に「周りと同じ」にせず、施術時間や内容、提供できる価値を基準に設定します。例えば同じ施術時間でも、説明やアフターケアを充実させることで付加価値が高まり、適正な価格を提案しやすくなります。複数回利用してもらえるように回数券やセットメニューを用意するのも有効です。こうすることで患者さんにとってもお得感があり、安定した収入につながります。
顧客満足度を高めながら単価を上げる方法
単価を上げるためには、価格以上の満足感を提供することが欠かせません。院内の清潔感や雰囲気、受付対応の丁寧さ、施術後のセルフケア指導など、小さな工夫が積み重なって「ここなら払う価値がある」という印象を強めます。また、患者さんの悩みに合わせて施術内容をカスタマイズし、効果を実感してもらうことで自然とリピートや紹介につながります。こうした取り組みは単価アップだけでなく、院の信頼性やブランド力向上にも貢献します。
数字に強くなくてもできる!収支改善を継続する仕組みづくり

定期的な収支チェックの習慣化
収支改善は一度見直して終わりではなく、定期的に振り返ることで成果が積み上がります。月に一度、売上と経費を集計し、来院数や平均単価、粗利などの主要な数字だけを確認するだけでも十分です。これを習慣化することで、異常値や改善点にすぐ気づけ、早めの対応が可能になります。最初は時間がかかっても、回数を重ねるうちに短時間で集計できるようになり、負担が減ります。
スタッフと共有することで改善が進む理由
数字を経営者だけが把握していると、改善のスピードが遅くなりがちです。来院数やリピート率、経費などの基本的な数字をスタッフとも共有することで、現場レベルでの工夫や提案が出やすくなります。例えば受付担当者が予約の取り方を工夫したり、施術者が回数券提案を強化したりと、全員が同じ目標に向かうことで成果が出やすくなります。数字の共有は、スタッフのモチベーションアップにもつながります。
補助金・助成金を活用した設備投資や改善策
接骨院の経営改善には、補助金や助成金の活用も有効です。新しい設備やシステム導入、業務効率化に必要な投資をサポートしてくれる制度が多くあります。例えば業務改善助成金や小規模事業者持続化補助金など、条件を満たせば負担を抑えて導入できます。これにより経営数字を無理なく整えつつ、院のサービス向上や差別化にもつながります。情報は定期的にチェックし、信頼できる専門家に相談しながら進めると安心です。