雇用調整助成金とは?2025年版 最新支給額と要件を徹底解説
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
雇用調整助成金とは?制度の概要と目的
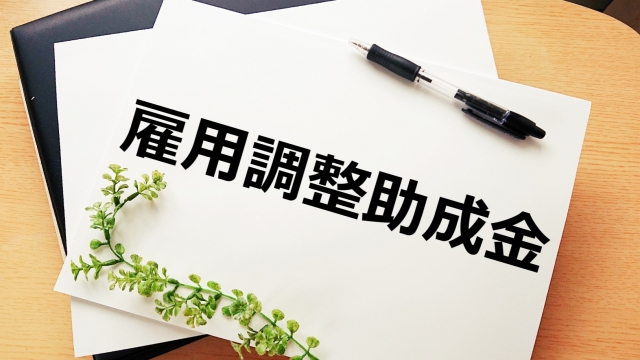
雇用調整助成金の目的
雇用調整助成金とは、経済的な理由で事業の縮小を余儀なくされた企業が、従業員を解雇せずに雇用を維持するための制度です。景気の悪化や感染症の流行、自然災害などで来客数が減り、収益が落ち込むとスタッフのシフトを削減する必要が出てきます。このとき、スタッフを守るために企業が休業や教育訓練を実施すると、国がその費用の一部を助成します。目的は、働く人が職を失うリスクを減らし、地域経済を安定させることです。
制度の基本的な仕組み
事業主は、休業や教育訓練を行った従業員に対して休業手当や訓練費用を支払います。その支払額の一部を国が助成する仕組みです。助成の対象は雇用保険に加入している従業員であり、事業主が雇用調整助成金の要件を満たしている必要があります。これにより、事業活動を一時的に縮小しながらも雇用を守ることが可能になります。
接骨院・鍼灸院でも利用できる理由
接骨院や鍼灸院は、地域医療やリハビリの役割を担う事業所です。しかし、景気の悪化や外出自粛の影響で患者数が減少することがあります。こうした場合でもスタッフを守るために休業や教育訓練を行えば、雇用調整助成金の対象になります。多くの接骨院や鍼灸院は中小企業に分類され、条件を満たしやすいため、活用しやすい制度と言えます。
2025年版・雇用調整助成金の最新要件
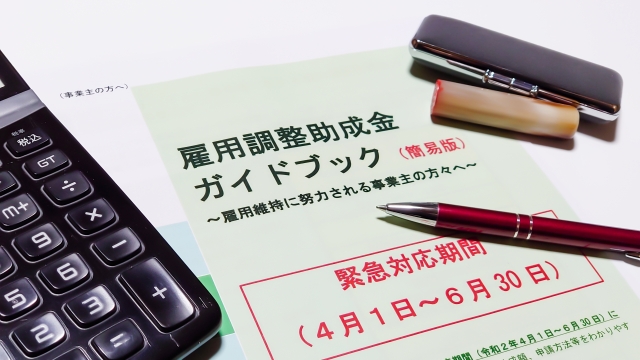
申請できる事業主の条件
雇用調整助成金を利用するには、まず事業主が雇用保険の適用事業主である必要があります。つまり、スタッフを雇用し、雇用保険に加入させていることが条件です。加えて、経済的な理由で事業を縮小せざるを得ない状況であることが求められます。具体的には、売上が一定割合以上減少している場合や、取引の減少によって業務が縮小しているケースが該当します。接骨院や鍼灸院は地域の需要に左右されやすいため、この条件に該当するケースが少なくありません。
労使協定と休業・教育訓練の要件
助成金を申請する際には、スタッフと合意の上で休業や教育訓練を実施する必要があります。休業の場合は所定労働日の全日にわたる休業が対象です。教育訓練を行う場合には、訓練計画を策定し、対象となる日数や内容が一定の基準を満たしている必要があります。労使で合意をしっかり取っていることが、申請時の重要なポイントです。
対象となる従業員と雇用保険の条件
対象となるのは雇用保険に加入している従業員です。さらに、休業や教育訓練の開始前日に6か月以上雇用されていることが原則とされています。短期的な雇用契約のスタッフであっても、条件を満たせば対象になります。接骨院や鍼灸院では受付スタッフや施術補助スタッフが該当することが多く、幅広く活用できる可能性があります。
雇用調整助成金の支給額と助成率

中小企業と大企業で異なる助成率
雇用調整助成金の助成率は、事業規模によって異なります。中小企業では、従業員に支払った休業手当や教育訓練費用の3分の2が助成対象となります。大企業の場合は2分の1です。接骨院や鍼灸院の多くは中小企業に分類されるため、比較的高い助成率でサポートを受けられるのが特徴です。
1日あたりの上限額と支給日数の制限
助成額には1日あたりの上限があります。2025年の最新情報では、1人1日あたり8,870円が上限です。助成を受けられる日数にも制限があり、1年間で100日まで、3年間で150日までと決められています。これにより長期間にわたる雇用維持の取り組みも支援されますが、この他にも様々な基準が定められていますので、計画的な利用が求められます。
教育訓練・出向の場合の加算措置
休業だけでなく、従業員を対象とした教育訓練や出向を実施する場合には、加算措置があります。教育訓練を行えば1日あたり1,200円の加算、出向の場合は出向元と出向先での調整費用が助成対象になります。接骨院や鍼灸院では、スタッフのスキルアップを目的とした研修や新たな技術習得のための教育訓練を組み合わせることで、さらに助成を受けやすくなります。
接骨院・鍼灸院が活用するメリットと申請の流れ

雇用維持に役立つ活用メリット
接骨院や鍼灸院は、患者数の変動に左右されやすく、景気や季節要因で売上が大きく変わることがあります。雇用調整助成金を活用することで、患者数が減って収入が落ち込んだ場合でもスタッフの雇用を守ることができます。スタッフの離職を防ぎ、長期的に安定したチームを維持することは、患者との信頼関係にも直結します。さらに、教育訓練を活用すれば、スタッフの技術力や接客力を高めることができ、サービスの質向上にもつながります。
申請の手順とスケジュール
申請の流れは大きく分けて3段階です。まず、雇用調整を行う計画を立て、スタッフとの協定を締結します。次に、労働局に休業や教育訓練の実施計画を提出し、承認を受けます。そして実施後、実績に基づいて助成金の支給申請を行います。初めての申請では手続きに時間がかかることもありますので、スケジュールには余裕を持つことが大切です。
申請に必要な書類一覧
申請には多くの書類が必要です。計画段階では休業等実施計画届や協定書、教育訓練の内容を示す資料などを準備します。支給申請時には支給申請書、助成額算定書、休業実績一覧表、給与台帳や出勤簿などの証拠書類が必要になります。接骨院や鍼灸院ではスタッフ数が限られていることが多いため、書類の準備や管理を早めに行うことが成功のポイントです。
申請時の注意点とよくある失敗
申請時に多い失敗は、必要書類の不足や記載内容の不備です。例えば、休業日数や休業手当の計算ミスは審査を遅らせる原因になります。また、労使協定の取り交わしを忘れていたり、計画の変更を届け出ていなかったりすると、不支給の可能性も出てきます。申請は細かな確認が必要であり、手順を正しく理解しておくことが大切です。
専門家に相談するメリット
助成金の申請は複雑で、初めての経営者にとっては負担になることがあります。社会保険労務士などの専門家に相談すれば、手続きの流れをスムーズに進められるだけでなく、不備による不支給リスクを減らせます。専門家に依頼するコストはかかりますが、確実に助成金を受け取るためには有効な選択肢です。
まとめ:雇用調整助成金を活用して雇用と経営を守る

制度活用で経営を安定化させる
雇用調整助成金は、経営が厳しい状況にある接骨院や鍼灸院にとって、従業員の雇用を守る重要な制度です。スタッフを解雇せずに済むことで、患者との信頼関係を維持しながら経営の立て直しを図ることができます。教育訓練を活用すれば、サービスの質向上にもつながり、長期的な経営安定に寄与します。
今後の経営改善に向けた次の一歩
制度を活用して雇用を維持できたら、次は経営改善に取り組むことが重要です。広告や集客施策の見直し、スタッフ教育の強化、ITの活用など、収益基盤を強化する方法はいくつもあります。雇用調整助成金はあくまで一時的な支援ですが、制度をきっかけに経営を見直すことで、より強い組織づくりが可能になります。経営者としての視点を広げ、地域に選ばれる接骨院・鍼灸院を目指しましょう。



