患者離れを防ぐ!接骨院・鍼灸院が取り組むべき改善策5選
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
患者離れの主な原因とは?

患者離れが起こる背景には、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。施術そのものの質だけでなく、対応の丁寧さ、院内の雰囲気、通いやすさなど、患者が「また来たい」と思えるかどうかのポイントは意外に多いものです。ここでは、接骨院・鍼灸院における患者離れの代表的な原因を整理して解説していきます。
技術面での不満
施術効果が実感できない
接骨院や鍼灸院を訪れる患者は、痛みや不調の改善を目的にしています。そのため、数回通っても効果が感じられない場合、「ここに通っても意味がないのでは」と感じて離脱することがあります。とくに症状が重い患者ほど、改善の兆しが見えないと不安が募り、他の治療院に期待を寄せて転院する傾向が強くなります。
担当者のスキルにばらつきがある
施術者が複数在籍している院では、担当によって技術の差を感じさせてしまうことがあります。一度信頼を得たとしても、他の施術者に変わったことで「前回と違って不安」「満足感が得られない」と感じた患者は、離れていく可能性が高くなります。技術レベルのばらつきは、患者の不信感を生む大きな原因になります。
接遇・対応への不満
コミュニケーション不足
施術だけでなく、患者との会話や説明も信頼関係を築くうえで非常に重要です。初診時の問診が浅かったり、施術中に状態説明がなかったりすると、患者は「自分のことを理解してくれていない」と感じてしまいます。このようなすれ違いは、患者が安心して通い続けるモチベーションを下げてしまいます。
スタッフの印象が悪い
受付や電話対応など、施術以外の接点も患者体験に大きく影響します。挨拶がない、声が小さい、無愛想といった印象は、院全体の印象を悪くします。たとえ施術の質が高くても、対応が悪ければ患者は「また行こう」とは思いません。日常的な接遇意識の差が、結果的に患者の定着率に響くのです。
環境やサービス面の問題
予約が取りづらい
「次の予約が2週間後しか取れない」「電話がつながらない」など、通いたいときに通えない状況が続くと、患者は通院をやめてしまいます。とくに慢性的な不調に悩む方にとっては、継続的な通院が必要です。予約の取りづらさは、患者の通院リズムを乱し、離脱を招きやすくなります。
院内の雰囲気に課題がある
院内が雑然としていたり、掃除が行き届いていない場合、無意識のうちに患者は不快感を覚えます。また、音楽がうるさすぎたり、照明が暗すぎたりといった空間の配慮不足も来院意欲に影響します。「また来たい」と思わせるには、清潔感と安心感のある空間づくりが欠かせません。
接骨院・鍼灸院が実践すべき5つの改善策
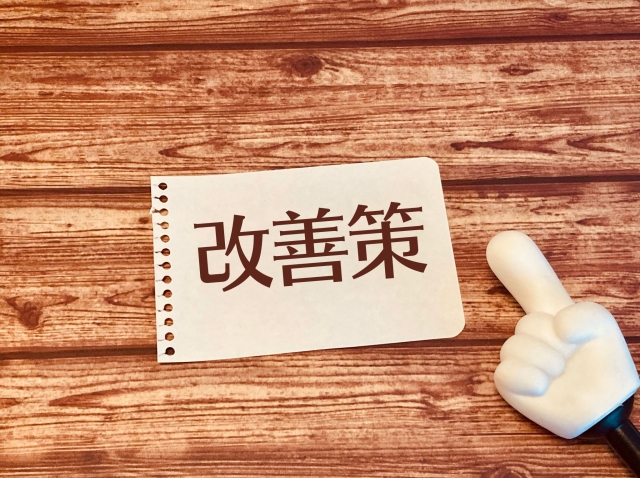
患者離れを防ぐためには、単に施術の質を高めるだけでは不十分です。多くの院が似たようなサービスを提供する中で、選ばれ続けるためには「再来院したくなる理由」を作る必要があります。ここでは、実際に効果が見込める5つの具体的な改善策をご紹介します。
施術スキルの向上と定期的な研修
患者の信頼を得るには、まず施術の技術を高めることが基本です。とくに、慢性疾患やスポーツ障害などの専門的な分野では、より深い知識と技術が求められます。そのためには、外部研修やセミナーへの参加、スタッフ同士の勉強会の実施などが効果的です。最新の技術や理論を取り入れることで、患者の症状改善につながり、「ここなら信頼できる」と感じてもらえる可能性が高まります。
差別化された専門メニューの導入
競合院との差別化を図るには、施術内容に独自性を持たせることが重要です。例えば、「肩こり専門」「産後骨盤矯正」「スポーツパフォーマンス向上」など、特定のニーズに応える専門メニューを設定することで、「あの悩みにはあの院」としての認知が広がります。また、専門性を打ち出すことで、他院に移る理由を減らし、固定ファンの獲得にもつながります。
アフターフォローと情報提供の充実
施術が終わった後も患者とつながりを持つことが、リピートにつながる大きな要素です。たとえば、施術後の体調変化をLINEでフォローしたり、自宅でできるストレッチやセルフケアのアドバイスを行ったりすることで、患者に寄り添う姿勢を示せます。こうしたサポートは「また相談したい」と思わせるきっかけになります。
患者との信頼関係を築くコミュニケーション
患者の不安や悩みに寄り添い、しっかりと話を聞く姿勢は、技術と同じくらい重要です。初回の問診時にしっかりと背景を把握し、毎回の施術時に「前回と比べてどうか」「今後の見通しはどうか」といった丁寧な説明をすることで、患者は安心感を得ます。信頼関係が築かれると、多少の不調や不便があっても他院に移る可能性は低くなります。
利便性を高める予約・通院システムの整備
「通いやすさ」もリピートに大きく影響します。最近では、電話よりもLINEやWebでの予約を好む患者が増えているため、スマホで完結できる予約システムの導入は有効です。また、土日診療や夜間診療など、ライフスタイルに合わせた柔軟な対応ができると、忙しい患者にも選ばれやすくなります。通院のハードルを下げることで、自然と再来率も向上します。
改善策を定着させるための運用ポイント

せっかく改善策を講じても、それが現場で継続されなければ意味がありません。施策を一時的に導入するのではなく、日々の業務の中にしっかりと根付かせるためには、院全体での意識共有と仕組み化が必要です。ここでは、改善を継続させるために重要な運用のポイントを紹介します。
スタッフ全員での共有と目標設定
改善策を定着させるには、まずスタッフ全員がその必要性と目的を理解していることが前提です。院長だけが意識していても、現場での対応にバラつきが出てしまえば、患者に不安を与えてしまいます。そのためには、定期的にミーティングを行い、「なぜこれをやるのか」「どこを目指しているのか」を明確に伝えることが重要です。
また、目標設定も欠かせません。「今月はリピート率◯%を目指す」「患者アンケートの満足度を◯点以上にする」など、数値として可視化することで、スタッフの意識が高まり、行動にも一貫性が生まれます。
定期的な振り返りと改善サイクルの構築
一度決めた施策が常に正しいとは限りません。現場で実施してみてうまくいかなかった点、患者からの反応が薄かった施策などは、随時見直しが必要です。そのためには、定期的な振り返りを行い、良かった点・改善すべき点をスタッフ全員で共有する場を設けることが大切です。
PDCA(計画→実行→評価→改善)のサイクルを習慣化することで、施策の質は自然と高まり、患者満足度の向上にもつながっていきます。「やって終わり」ではなく、「やった後の評価と改善」が、患者離れを食い止めるうえで重要な鍵となるのです。
患者離れを防ぐために今すぐ始められること

改善策といっても、「何から始めればいいかわからない」という方も多いかもしれません。しかし、患者離れを防ぐためには、まず現状を把握し、小さなことから着実に取り組むことが大切です。このセクションでは、特別な設備や費用をかけずに、今すぐ始められる実践的なアクションを紹介します。
院内のチェックリストを作成する
日々の業務に追われる中で、基本的な対応や環境整備がおろそかになっていないかを見直すには、チェックリストの活用が有効です。たとえば、「笑顔で挨拶できているか」「施術前に症状の確認をしているか」「院内は清潔か」といったチェック項目を設け、毎日確認することで、サービスの質を安定させることができます。
このリストは、スタッフ全員で作成し、共通認識を持つことで、院内の一体感も生まれます。改善策を日常業務に落とし込み、自然に実践できる仕組みを作ることが、継続のカギとなります。
既存患者へのヒアリングを実施する
患者離れの本質的な原因を知るには、実際に通っている患者の声を聞くのが最も確実です。満足している点、不安を感じた点、改善してほしい点などを、定期的にヒアリングすることで、患者の本音を把握できます。
アンケート形式でも良いですし、施術中の会話の中でさりげなく意見を聞くのも良いでしょう。集めた声をもとに改善を図ることで、「この院はちゃんと話を聞いてくれる」と感じてもらい、患者との信頼関係も深まります。
まとめ|リピート率向上は日々の積み重ねから

接骨院・鍼灸院における「患者離れ」は、どの院でも直面しうる課題です。しかしその原因を明確にし、的確な対策を地道に積み重ねていけば、リピート率は確実に改善できます。
小さな改善が大きな成果に
施術スキルの向上や予約システムの見直しといった大きな取り組みだけでなく、毎日の笑顔や丁寧な説明、院内の清潔感など、小さな気配りも患者の満足度に直結します。何気ない行動の積み重ねが、最終的に「また通いたい」と思ってもらえる大きな要因になります。
継続的な取り組みが信頼を生む
一度始めた改善策を継続することが、患者との信頼関係を育む最大のポイントです。すぐに効果が現れなくても、焦らずに地道に続けることで、「ここなら安心して通える」と感じてもらえるようになります。院全体で取り組みを共有し、改善を日常業務に落とし込むことで、安定した経営と患者満足の両立が可能になります。



