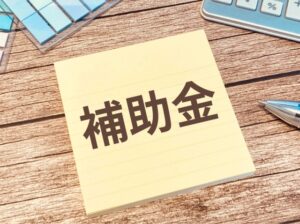第18回小規模事業者持続化補助金を徹底解説|成功するための5つのポイント
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
第18回小規模事業者持続化補助金とは?概要と目的を解説
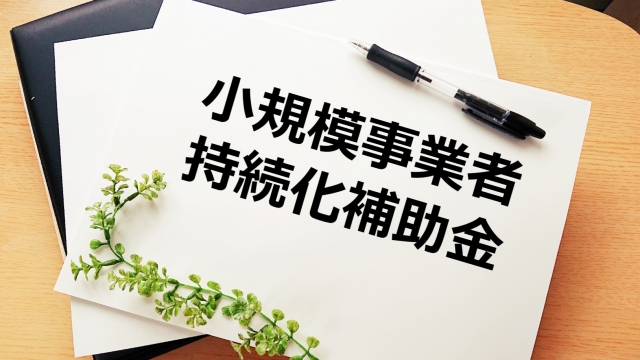
補助金の目的と背景
第18回小規模事業者持続化補助金は、地域経済を支える小規模事業者の経営をサポートするために設けられた制度です。少子高齢化や人手不足が深刻化する中、事業を継続し発展させるためには、販路開拓や業務効率化が欠かせません。補助金は、こうした取り組みにかかる経費を支援し、持続可能な経営を実現することを目的としています。経営者が将来を見据えた計画を立て、自社の強みを活かした施策を行えるよう後押しする仕組みです。
対象者と補助対象経費
対象となるのは、常時使用する従業員数が5人以下の商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)、または20人以下の製造業などの小規模事業者です。補助対象経費には、機械装置の導入費用、広告やチラシの作成、ウェブサイト構築、展示会出展費用など、販路開拓や業務効率化に必要な経費が含まれます。具体的には、旅費や新商品開発費、借料、外注費なども補助対象となるため、幅広い取り組みに活用できます。
第18回小規模事業者持続化補助金の申請スケジュールと注意点

公募期間と締切
第18回の公募要領は2025年6月30日に公開されました。申請の受付開始は同年10月3日、締切は11月28日(予定)です。事業支援計画書(様式4)の発行締切は11月18日(予定)となっており、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。締切間際は商工会議所の予約が取りづらくなることも多いため、早めの相談と計画書作成を心がけましょう。
電子申請システムの利用方法
この補助金は電子申請システムを通じてのみ受け付けています。郵送での提出は認められていません。事前にGビズIDを取得し、システムへのログイン準備を進める必要があります。電子申請では、経営計画書や補助事業計画書などをPDF形式でアップロードするため、正しく入力しダウンロードした書類を準備しておくことが大切です。操作方法が不安な場合は、事前に公式サイトでマニュアルを確認しましょう。
👇GビズIDの取得については、過去記事で解説しています👇
https://emio.jp/news/【接骨院・鍼灸院でも活用可能】補助金申請に必/
申請時の注意事項
申請の際は、書類不備や内容の誤りを避けることが採択への第一歩です。経営計画や補助事業計画の内容は具体性と実現可能性をしっかり示す必要があります。また、締切日までに商工会議所での確認を受け、事業支援計画書を取得することも必須です。相談予約の遅れや書類の準備不足が致命的になるため、スケジュールを逆算して進める意識が欠かせません。
商工会議所での相談を成功させる準備とポイント

相談前に準備すべきこと
商工会議所に相談する前に、まず自分の事業の現状を整理しましょう。売上や課題、将来の目標を言葉にできるようにしておくことで、相談がスムーズに進みます。また、補助金を活用して何を実現したいのか、導入したい設備や取り組みのイメージを明確に持つことが重要です。外部のコンサルタント任せにせず、事業主自身がしっかりと自分の言葉で説明できるようにしておく準備が欠かせません。
相談予約と当日の流れ
多くの商工会議所では事前予約が必要です。電話やウェブサイトを通じて希望日時を伝え、予約を取りましょう。相談当日は、予約時間に遅れずに訪問し、担当者に具体的な質問や課題を伝えることで的確なアドバイスを得られます。時間を有効に使うために、相談内容をメモして持参するのもおすすめです。商工会議所の職員は補助金の申請手続きに詳しく、実務的なアドバイスを提供してくれる心強いパートナーです。
相談時に持参すべき書類
相談時には、経営計画書(様式2)、補助事業計画書(様式3)などの必要書類をあらかじめ電子申請システムで入力し、PDFを印刷して持参しましょう。代表者の身分証明書も必要になる場合があります。特に事業承継加点を希望する場合は必須です。会社案内や最近の決算書、確定申告書など、事業内容や財務状況を説明できる書類もあると役立ちます。これらを事前に揃えることで、相談が円滑に進み、的確なアドバイスを受けやすくなります。
申請に必要な書類とその準備方法

経営計画書(様式2)の作成ポイント
経営計画書(様式2)は、自社の現状や課題、今後の方向性を具体的に示す重要な書類です。単に「売上を増やしたい」という抽象的な目標ではなく、どのような取り組みで売上を伸ばすのかを詳しく説明することが求められます。自社の強みや地域のニーズを踏まえ、具体的な数値目標やスケジュールを盛り込むことで、説得力のある計画書になります。商工会議所の職員と相談しながらブラッシュアップするのも効果的です。
補助事業計画書(様式3)の作成ポイント
補助事業計画書(様式3)は、補助金を活用して実施する事業内容を詳細に記載する書類です。例えば、導入する機械装置の種類やその費用、期待される効果などを具体的に書くことがポイントです。事業の実現可能性を示し、採択後の計画遂行を担保できる内容であることが重要です。見積書や仕様書を用意して内容を裏付けると、審査担当者に信頼感を与えることができます。
身分証明書やその他の関連書類
申請者本人の身分証明書(運転免許証など)も必要です。特に事業承継加点を希望する場合は、必須書類として提出を求められることがあります。また、会社案内、サービス内容が分かるパンフレット、最近の決算書や確定申告書など、事業の信頼性や実績を説明できる資料を用意しておくとスムーズです。準備不足を避けるため、商工会議所で事前に必要書類のリストを確認し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
採択率を高めるための5つの成功ポイント
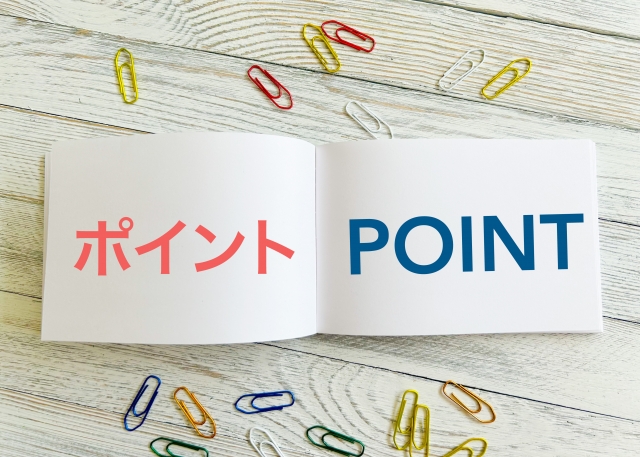
1. 経営計画の具体性を高める
経営計画書は単なる形式ではなく、事業の将来を示す設計図です。売上目標や顧客層の分析、地域での強みを盛り込み、具体的な施策を記載することで審査員に本気度を伝えられます。抽象的な表現を避け、数字や事例を交えて説明することで説得力を高めましょう。
2. 補助事業計画の実現可能性を示す
補助金を使った取り組みが本当に実現できるかを伝えることが重要です。導入予定の機械やサービス内容を具体的に説明し、なぜそれが必要なのか、どのように運用するのかを明確にしましょう。現実味のあるスケジュールや予算計画を提示することで、計画の信頼性が高まります。
3. 必要書類の不備をなくす
採択率を下げる最大の原因の一つが書類の不備です。申請書類の内容に誤字脱字がないか、必要な情報が漏れていないかを必ず確認しましょう。電子申請システムでの提出形式やファイル名のルールにも注意が必要です。提出前には必ず商工会議所などでチェックを受けることをおすすめします。
4. 商工会議所との連携を密にする
商工会議所は補助金申請の心強いパートナーです。相談を早めに予約し、担当者に計画の内容を共有することで、改善点や注意事項をアドバイスしてもらえます。特に初めて申請する場合は、細かい疑問を積極的に相談することが成功への近道です。
5. 余裕を持ったスケジュール管理
締切直前は相談が集中し、予約が取りづらくなることも珍しくありません。前回サポートを行った東京23区内の商工会議所地区の方は、2週間先まで予約が取れず、申請締切り前日のみ空きがあり、ギリギリで様式4の発行が間に合ったという方もいらっしゃいます。
余裕を持ってスケジュールを組むことで、計画書の精度を高め、書類の不備を防げます。電子申請システムの操作に慣れる時間も確保し、計画的に進めることが成功への近道です。