「うちは申請できる?」接骨院・鍼灸院が知っておくべき人材確保等支援助成金の要件とポイント
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
人材確保等支援助成金とは?接骨院・鍼灸院が知っておきたい基本概要
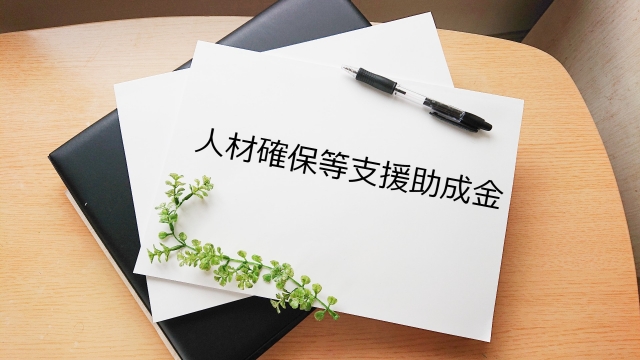
助成金の目的──人手不足と定着を同時に解決するために
人材確保等支援助成金は、職場環境を整え、離職を減らし、働き続けやすい院づくりを後押しする制度です。少子高齢化でスタッフの確保が難しくなるなか、待遇や働き方の見直しに踏み出す小規模事業者を支える狙いがあります。接骨院・鍼灸院でも、日々の施術・受付・事務まで幅広い業務が集中しやすく、負担の偏りが退職の引き金になりがちです。この助成金は、そうした現場の課題に対して“仕組み”と“道具”の両面から改善を進めるための資金面のサポートだと捉えると理解しやすいでしょう。
何に使えるのか──制度導入と業務負担軽減機器の二本柱
対象は大きく二つに分かれます。ひとつは賃金規定や人事評価、1on1などの雇用管理制度の整備。もうひとつは、作業の重さや回数を減らす業務負担軽減機器の導入です。前者は「公平で納得感のあるルール」を作る取り組み、後者は「身体的・時間的な負担を減らす設備投資」と考えるとよいでしょう。制度で不満や不公平感を防ぎ、機器で作業のムダや疲労を減らす。両輪で回すことで、結果的に離職の芽を小さくできます。
接骨院・鍼灸院に関係するのはなぜ?
小規模の院にとって、新人教育のやり直しや人手不足は売上と施術品質に直結します。業務の属人化が進むほど、特定スタッフの負担が膨らみ、休職や退職のリスクが高まるのも現実です。本助成金を活用すれば、評価や賃金のルールを整え、シフトや業務分担の見える化を進めつつ、受付・清掃・カルテ入力などの反復作業を機器やソフトで軽くできます。結果として、スタッフが「ここで働き続けたい」と思える環境に近づき、採用の間口も広がるはずです。
接骨院・鍼灸院は対象になる?申請できる事業者の条件とチェックポイント

対象となる事業者の基本条件
人材確保等支援助成金は、誰でも自動的に受けられるわけではありません。まず大前提として、雇用保険の適用事業所であることが必要です。これは、スタッフを雇用し雇用保険に加入させている接骨院・鍼灸院であれば、多くの場合で該当します。また、原則として中小企業または小規模事業者であることも条件に含まれます。接骨院や鍼灸院はこの枠に該当するケースが大半のため、この点で心配する必要はそれほどありません。
さらに、過去に不正受給や助成金の返還命令を受けていないこと、労働関係法令を遵守していることなども基本条件として求められます。例えば、残業代の未払いがある、雇用契約書が整備されていないなどの場合は、申請が通らないこともあるため、事前の確認が欠かせません。
「うちは申請できるのか」を判断する3つのチェックポイント
自院が対象となるかどうかを判断するためには、次の3点を確認してみましょう。
まず一つ目は、最低賃金の引き上げ計画が立てられるかどうかです。助成金の申請には、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げることが条件となるケースがあります。特に人手不足の現場では、この条件を満たすことが助成対象への第一歩となります。
二つ目は、新たな制度や機器を導入する意思があるかどうかです。すでに導入済みの仕組みや機器の更新だけでは助成の対象にならない場合が多いため、現場の働き方を改善するための新しい取り組みが必要です。
三つ目は、離職率の改善が見込めるかどうかです。制度導入や設備投資によって、スタッフの働きやすさが向上し、1年後に離職率が下がる可能性があるかどうかが審査の大きなポイントとなります。単なるコスト補助ではなく、「定着率改善につながるか」が重視される点を押さえておきましょう。
接骨院・鍼灸院ならではの活用のポイント
接骨院や鍼灸院は、少人数体制の現場が多く、施術・受付・事務処理などの業務が一人に集中しがちです。そのため、業務効率を高める取り組みやスタッフの待遇改善は、離職率の低下に直結します。人材確保等支援助成金は、まさにこうした現場での課題解決を後押しする制度です。
「うちは対象になるのか分からない」と感じている場合でも、多くの接骨院・鍼灸院は条件を満たしていることがほとんどです。まずは、自院が基本的な条件をクリアしているか、そして改善の余地がある取り組みがあるかどうかをチェックしてみることが、申請の第一歩となります。
助成対象となる主な取り組み内容と費用補助の仕組み

助成対象は大きく2つ──「制度の整備」と「機器の導入」
人材確保等支援助成金の活用で押さえておくべきポイントは、対象となる取り組みが大きく二つに分かれるという点です。ひとつは、雇用管理制度の整備と呼ばれる「仕組み」の部分です。もうひとつは、業務負担軽減機器の導入と呼ばれる「設備投資」の部分です。この二本柱が、助成金の中心的な対象となります。
制度の整備とは、賃金規定や諸手当、人事評価制度、健康づくり制度、1on1やメンター制度などの職場活性化策といった「人が働き続けやすいルールや環境」を整える取り組みを指します。例えば、評価基準が曖昧でスタッフが不満を感じていたなら、人事評価制度の導入が助成対象になります。健康診断の仕組みやメンタルケア体制の整備も該当するケースが多く、接骨院・鍼灸院の規模でも現実的な取り組みが可能です。
一方の業務負担軽減機器の導入は、スタッフの作業時間や体への負担を軽くするための設備投資です。電子カルテの記録支援ソフトや、患者データ管理システム、受付自動化ツール、施術機器の自動昇降台など、現場業務を効率化する機器が該当します。直接的な作業時間を減らし、スタッフが本来の業務に集中できる環境をつくることが目的です。
助成額と補助率──どこまで支援してもらえるのか
助成金の金額は、導入する取り組みや条件によって異なります。例えば、雇用管理制度の整備については、1制度あたり最大80万円(賃金要件を満たす場合は100万円)まで助成されます。複数の制度を導入すれば、それぞれが対象となるため、まとまった支援を受けられる可能性があります。
業務負担軽減機器の導入では、対象経費の1/2が助成され、賃金要件を満たすと62.5%まで補助率が引き上げられます。上限は150万円(賃金要件達成時は187.5万円)となっており、中小規模の接骨院や鍼灸院にとっては非常に現実的な金額といえます。単なる備品購入ではなく、「離職率低下につながる機器かどうか」が審査のポイントとなる点に注意が必要です。
導入機器の具体例──現場で役立つ活用シーン
現場で実際に助成対象となる機器の一例として、作業姿勢を改善するエルゴノミクス機器(電動昇降ベッド、移乗補助機器など)、施術補助を効率化する自動化機器(自動受付端末や自動会計機)、記録・見守りを省力化するICT機器(施術記録ソフト、顧客管理システム)などが挙げられます。
特に接骨院や鍼灸院の現場では、受付・会計・カルテ入力などの「付帯業務」が多く、施術以外の時間がスタッフの負担となっていることも珍しくありません。助成金を活用してこうした作業を軽減すれば、残業削減やスタッフの定着、患者対応の質向上といった複数の効果が期待できます。
初めてでも安心!申請までの流れと準備しておくべき書類

申請の全体像をつかもう──4つのステップで考える
人材確保等支援助成金の申請は、複雑そうに見えても流れさえつかめば決して難しくありません。大きく分けると、①計画の作成と認定申請、②制度や機器の導入、③離職率の評価、④支給申請という4つのステップで進みます。どの段階で何をするかを事前に理解しておくと、手続きがスムーズになります。
まず最初に行うのが「雇用管理制度等整備計画の作成と認定申請」です。これは、「どのような制度や機器を導入するか」「どのように職場を改善するか」といった計画をまとめ、都道府県労働局へ提出する作業です。計画は、導入開始の1か月〜6か月前までに提出する必要があり、期限を過ぎると申請そのものができなくなるので注意が必要です。
次に、認定された計画に基づいて「制度や機器の導入」を行います。このとき、認定を受ける前に機器を購入したり制度を運用し始めてしまうと対象外になるため、順序を間違えないことが重要です。導入は計画に定めた期間内に完了させなければなりません。
続いて行うのが「離職率の評価」です。導入後1年間の離職率が、計画提出前の1年間よりも1ポイント以上下がっているかが問われます(従業員数が9人以下の場合は上回らないことが条件)。この条件を満たせなければ、助成金は支給されない点に注意しましょう。
最後のステップは「支給申請」です。評価期間が終わった後、2か月以内に必要書類を添えて申請します。ここまでが一連の流れであり、すべてのステップを計画的に進めることが助成金活用の鍵となります。
申請時に必要となる書類と準備のポイント
初めて申請する場合、「どんな書類が必要なのか」がわかりにくいと感じる方も多いでしょう。申請するコースによって異なりますが、代表的なものには、雇用管理制度等整備計画書、労働保険関係の書類、就業規則や賃金規程の写し、従業員名簿、離職率の計算資料、機器購入の見積書・領収書などがあります。どれも後から慌てて準備するより、計画段階から少しずつ揃えておくと安心です。
また、書類の記載内容が不十分だったり、条件を満たしていないと判断されたりすると、審査が通らない場合があります。特に「離職率の算定根拠」や「新規導入であることの証明」などはよくチェックされるポイントなので、提出前に専門家や社労士に確認してもらうのも一つの方法です。
初めてでも不安にならないためのコツ
申請手続きを自力で進めるのは不安という声も少なくありません。ポイントは、「早めの準備」「正しい順序」「専門家の活用」の3つです。特に、計画書の作成や離職率の計算などは専門知識が求められる部分も多いため、社会保険労務士や中小企業診断士など、助成金申請のサポート経験がある専門家に相談すると安心です。
申請の流れ自体は決して複雑ではありませんが、ひとつでも抜け漏れがあると不支給になる可能性もあります。初めての場合こそ、全体像をつかみ、準備と確認を丁寧に進めることが成功の近道です。
まとめ|自院が対象かどうかを確認して助成金活用の第一歩を踏み出そう

まずは「対象になるかどうか」を知ることが最初のステップ
人材確保等支援助成金は、単なる資金補助制度ではありません。離職率の改善や働きやすい職場づくりという目的を持って設計されており、接骨院・鍼灸院のような小規模事業者でも十分に活用可能な支援策です。しかし、申請するためには「自院が対象になるか」「どの条件を満たす必要があるか」を最初に確認することが欠かせません。まずは雇用保険の適用事業所であるかどうか、労働法令を遵守しているか、最低賃金の引き上げや新しい制度の導入が可能かといった基本的な要件をチェックしましょう。
自院に合った活用方法を考えることで効果はさらに高まる
助成金を活用する意義は、単に費用負担を減らすことにとどまりません。制度の整備によって職場の透明性や納得感を高め、機器の導入によって作業効率を向上させることで、スタッフの働きやすさが大きく変わります。その結果、離職率の低下だけでなく、採用の強化やサービス品質の向上といった波及効果も期待できるのです。
また、助成金は「申請して終わり」ではなく、導入後の運用が重要になります。職場環境の改善は一度で完成するものではありません。定期的な見直しや改善を重ねることで、より良い職場づくりへとつながっていきます。
行動することで未来は変わる
「うちは対象になるのだろうか」「手続きが難しそう」と感じている方ほど、まずは情報を整理して一歩を踏み出すことが大切です。条件を確認し、制度の概要をつかみ、計画を立てるだけでも前進となります。必要であれば専門家に相談しながら、無理のない範囲で準備を進めてみましょう。
助成金は、現場の課題解決を後押しする大きなチャンスです。この記事をきっかけに、自院の環境改善とスタッフの定着という次のステージへ進むための一歩を踏み出してみてください。



