補助金・助成金を活用し交付されたお金に税金はかかる?接骨院・鍼灸院経営者が知っておくべき5つのポイント
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
補助金・助成金にかかる税金の基本を理解しよう

補助金・助成金を活用し交付されたお金に税金はかかるのか――多くの接骨院・鍼灸院が最初に気になる点です。結論から言えば、原則として課税対象となり、会計上は売上とは別枠の収益として処理します。ただし、災害関連の給付金など一部には非課税のものもあり、種類ごとの取り扱いを見極めることが重要です。当記事では、日々の施術収入とは性質の異なる「補助金というお金」がどのように課税に結びつくかを、専門用語を避けて整理します。制度を正しく理解すれば、余計な税負担や申告ミスを避けつつ、安心して設備投資や広報施策に資金を回せます。院の規模や経営スタイルにかかわらず共通する考え方から順に見ていきましょう。
所得税・法人税の課税対象となる仕組み
補助金や助成金は、患者さんからの施術代のように「サービスの対価」ではありませんが、院に流れ込むお金である点は同じです。そのため、原則として利益計算の対象に含められ、最終的な利益が増えれば、その分だけ法人税や所得税の負担が生じます。ここで押さえておきたいのは、「受け取った全額に税金がかかる」のではなく、「ほかの経費と合算して算出した利益」に対して税金がかかるという仕組みです。例えば、設備導入のために補助金を受け取った場合でも、機器の減価償却費や保守費用などの経費を含めたうえで利益が決まります。なお、コロナ禍の給付金のように法律で非課税とされたものも存在します。名称が似ていても扱いが異なることがあるため、交付要綱や通知文を必ず確認すると安心です。
営業外収益としての会計処理とは
会計上、補助金・助成金は多くの場合「営業外収益」に区分します。これは、施術という本業から得た売上と性格が異なるためで、患者数や単価の推移を分析するときに数字が混ざらないという利点があります。日々の売上は「どれだけ来院があったか」を映す体温計であり、補助金は経営を後押しする外部資金です。区分を分けることで、集客や単価改善の実力を正しく測れます。さらに、営業外収益として記録しておくと、金融機関や支援機関に提出する資料でも資金の出どころが明確になり、説明がスムーズになります。入金が決算をまたぐ場合には「未収入金」を使って期ずれを防ぐ処理が必要です。入金の証憑や交付決定通知の写しを、仕訳のメモと一緒に保管しておくと、後日の確認や税務調査でも迷いません。
接骨院・鍼灸院経営者が押さえるべき補助金・助成金の会計処理ポイント

補助金や助成金を正しく使うためには、税金だけでなく会計処理の基本も理解しておく必要があります。施術収入と違い、補助金は年度や事業計画に基づいて交付されるため、処理を誤ると後から申告修正が必要になったり、資金繰りに影響が出ることがあります。この章では、接骨院・鍼灸院経営者が特に注意すべき収益計上の時期や勘定科目の選び方など、現場で役立つポイントをやさしく解説します。
収益計上のタイミングと未収入金の扱い
補助金は申請しただけでは収益にならず、「受給が確定した時点」で初めて収益として計上します。多くの場合、交付決定通知書を受け取ったタイミングで記録しますが、実際の入金まで時間がかかることが少なくありません。その場合は、未収入金として一旦計上し、入金時に消し込む処理を行います。これを怠ると、決算書の数字が実態とずれ、翌期に収益が二重計上される恐れがあります。日付と金額を明確にメモしておくことが、後々の確認や税務調査の際にも有効です。
勘定科目の選定と圧縮記帳の活用方法
補助金は通常「雑収入」として処理されますが、設備投資に充てた場合には「固定資産圧縮記帳」という特例を使うことで課税所得を圧縮できます。例えば新しい施術機器を補助金で購入した際、補助金分を取得原価から差し引いて資産計上すれば、その分だけ利益が減り、税負担を抑えられます。圧縮記帳を利用するかどうかは任意ですが、制度を使わない場合は全額を資産計上し、その後の減価償却で少しずつ費用化する形になります。どちらが有利かは年度ごとの利益や設備導入計画によって異なるため、税理士など専門家と相談しながら判断することが望ましいでしょう。
消費税の扱いと補助金・助成金利用時の注意点

補助金や助成金は、接骨院・鍼灸院にとって貴重な資金源ですが、消費税との関係を誤解していると、思わぬ負担や手続きが発生することがあります。実は、補助金自体は基本的に消費税の課税対象外である一方、そのお金で購入した物品やサービスには通常通り消費税がかかります。この章では、その違いと注意点を整理し、安心して補助金を活用できるように解説します。
補助金・助成金が消費税非課税となる理由
補助金や助成金は、物品やサービスの対価ではなく、国や自治体が事業を支援する目的で交付するものです。そのため、受け取った時点で消費税を計上する必要はありません。例えば、新しい施術台を購入するために交付された補助金も、入金時に消費税が課されることはありません。ここを理解しておくと、消費税の申告や納税の際に「補助金も含めて計算しなければならないのではないか」という不安を解消できます。
補助金を使って購入した物品・サービスの消費税処理
注意が必要なのは、補助金で購入した物品やサービスには通常通り消費税がかかるという点です。例えば、補助金で最新の電気治療機器を導入した場合、その機器にかかる消費税は支払う必要があります。ただし、課税事業者であれば仕入税額控除を通じて一定の控除が可能です。補助金を受け取ったからといって控除できなくなるわけではありません。導入時には請求書や領収書を必ず保存し、補助金の用途と支払いの内訳を明確にしておくと、申告や会計処理がスムーズになります。
非課税となる補助金・助成金の具体例と確認方法
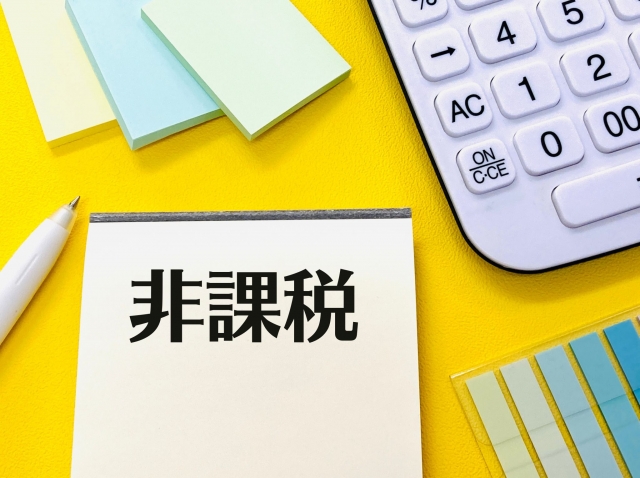
補助金や助成金の多くは課税対象ですが、なかには法律で非課税と定められているものも存在します。こうした制度を知らずに課税対象と誤認してしまうと、不要な申告や税負担が発生する恐れがあります。この章では、接骨院・鍼灸院経営者が特に注意すべき非課税補助金の具体例と、判断する際のポイントを解説します。
新型コロナ関連支援金や生活支援給付金など
代表的な非課税補助金として、新型コロナウイルス感染症に関連する各種支援金や特別定額給付金などがあります。これらは、国民生活や事業継続を守るために特別に交付されたもので、所得税法や関連通達で非課税とされました。接骨院・鍼灸院においても、緊急時の給付金や休業支援金を受け取った場合は課税対象外になることがあります。ただし、同じ「コロナ関連支援金」という名前でも、事業再構築補助金など設備投資系の補助金は課税対象です。名称が似ていても性質や目的によって扱いが異なるため、個別に確認することが大切です。
非課税対象かどうかを事前に確認する方法
非課税かどうかを判断するには、まず交付要綱や国税庁が出している取り扱い通知を確認するのが基本です。補助金の交付決定通知書や案内文に「課税」「非課税」などの記載があることもありますが、書かれていない場合は税務署や専門家に相談するのが確実です。特に接骨院・鍼灸院のように保険診療と自費診療が混在する事業形態では、税務区分が複雑になりがちです。あいまいなまま処理を進めるより、早めに確認しておくことで、後から修正する手間やペナルティを避けられます。
補助金・助成金を活用する接骨院・鍼灸院が税務上で失敗しないための実践ポイント
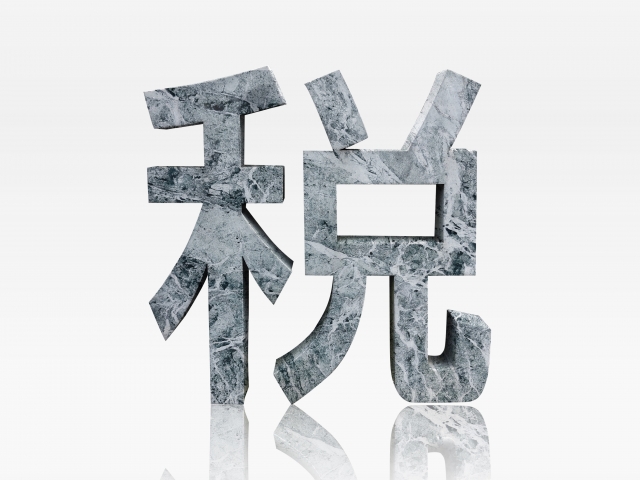
補助金や助成金は経営の強い味方ですが、使い方や処理方法を誤ると、せっかくの支援が逆に負担になることがあります。最後に、接骨院・鍼灸院経営者が税務面で失敗しないための実践的なポイントを整理します。ここまで解説してきた内容を実際の運営に落とし込むヒントとして活用してください。
書類保存と税務調査への備え
補助金の交付決定通知書や入金記録、補助金を使って購入した機器の請求書・領収書など、関連する書類はすべて一式そろえて保管しておくことが基本です。これにより、決算書や申告書を作成する際の根拠が明確になり、税務調査が入ったときにもスムーズに対応できます。保存期間は通常の帳簿書類と同様、少なくとも7年間が目安です。特に圧縮記帳を行った場合は、その計算根拠や仕訳メモも併せてファイルしておくと安心です。
税理士など専門家と連携するメリット
補助金や助成金の処理は、制度の内容や税務通達によって毎年細かく変わることがあります。経営者がすべてを把握するのは大変ですが、税理士など専門家と連携することで最新の情報を得られ、適切な処理方法を選択できます。また、どのタイミングで収益計上するか、圧縮記帳を使うかなど、利益や資金繰りの状況に応じたアドバイスも受けられます。こうしたサポートを活用することで、補助金制度を最大限に活かしつつ、税務上のリスクを最小限に抑えることができます。
emioでは、多くの接骨院をクライアントに持つ税理士もご紹介しております。(仲介料など、余分な費用はいただきません。)
自分一人で処理するのは限界かも・・・と思い始めている方、お気軽にご相談下さい。



