今年度増加中の不正受給事例と5つの防止策|接骨院・鍼灸院向け完全ガイド
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
今年度に増加している不正受給事例とは?
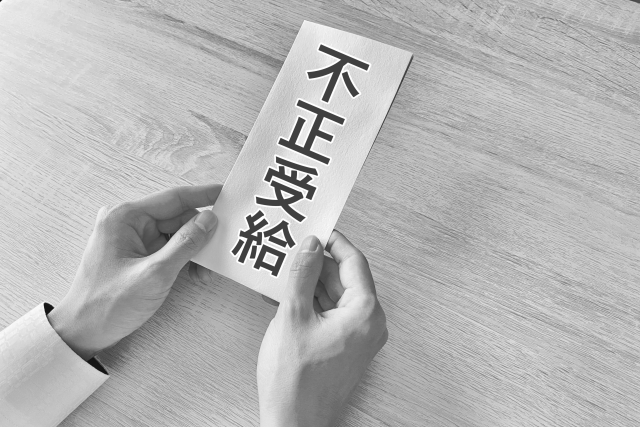
今年特に問題視される傾向
今年度、接骨院や鍼灸院を取り巻く補助金申請では、不正受給が深刻な課題として注目されています。経営を助ける制度が増えたことで申請のハードルは下がりましたが、その分「自己負担ゼロ」「キャッシュバック可」といった過剰な営業トークに流される例も目立っています。こうした動きが続くと制度全体の信頼性を損ない、結果的に審査や監査がより厳しくなる状況を生んでいます。経営者自身が内容をしっかり理解し、リスクを見極める姿勢が求められています。
実際に報告されている具体例
実際には、補助金を使って購入したソフトや機器を後から販売業者が全額返金することで、実質無料にする手法が問題視されています。また、申請に必要なIDやパスワードを他人に預けて手続きを任せるケースも増えています。さらに、研修を受講したと虚偽の申請をし、実際はメールで資料を送っただけだった事例もあります。こうした不正は、経営者が知らなかったとしても責任を問われ、返還請求や法的対応の対象となるリスクをはらんでいます。
接骨院・鍼灸院が陥りやすい不正受給パターン

ITツールの実質無料提供
接骨院や鍼灸院を対象にした営業で「実質無料で導入できます」とうたう提案が増えています。補助金を利用してソフトや機器を購入した後、販売業者が全額を返金する形で自己負担をなくす仕組みです。一見お得に思えますが、これは補助金制度の趣旨をゆがめる不正行為です。知らずに利用した場合でも、後から返還を求められるリスクがあり、経営に大きなダメージを与えます。
代理申請やID貸与
申請作業が複雑だと感じ、手続きを他人に任せたくなる経営者も少なくありません。しかし、申請に必要なIDやパスワードを他者に渡して代理申請をさせる行為は規約で禁止されています。申請内容を正しく理解しないまま他人任せにすることで、思わぬ不正申請につながり、最終的には事業者本人が責任を負うことになります。自分のIDは自分で管理し、内容をしっかり把握する意識が大切です。
研修・導入実態の偽装
補助金の対象に含まれる研修やコンサルティングは、実際に実施されなければなりません。しかし「受講したことにしておきましょう」と持ちかけられ、メールで資料を送っただけで研修を完了したことにするケースが報告されています。こうした行為は審査の際に特に重点的に確認され、証拠が不十分だと判断されれば不正受給とみなされます。導入の事実をしっかり記録し、説明できるようにしておくことが必要です。
他補助金との二重受給
経営を支えるために複数の補助金を活用したいという考え自体は問題ありません。ただし、同じ経費を別の補助金でも重複して申請することは禁じられています。例えば、同じソフトウェアの購入をIT導入補助金と別の補助金でそれぞれ請求する行為が該当します。審査の過程で過去の申請内容を照合する仕組みも強化されており、発覚した場合は返還だけでなく今後の申請停止処分を受ける可能性もあります。
事業実態の過少申告
補助金の要件をクリアするために、実際よりも従業員数を少なく申告したり、経営規模を小さく偽ったりする行為も問題です。「少しくらいなら大丈夫」という気持ちで書類を操作すると、調査で発覚した際に重大な不正として扱われます。接骨院・鍼灸院経営者は、公的な支援を受ける以上、正確で誠実な申請を行う責任があることを忘れてはいけません。
不正受給によるリスクとペナルティ
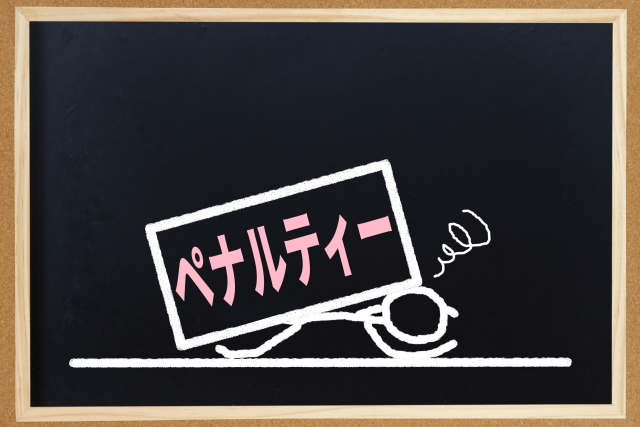
全額返還と加算金・延滞金
不正受給が発覚すると、まず補助金の全額返還を求められます。さらに受給額の20%程度の加算金や延滞金が上乗せされるケースもあります。これは「知らなかった」「少しだけだから」という言い訳では免れません。突然の大きな返金負担は、経営を直撃し、計画していた設備投資や運転資金に大きな影響を及ぼします。申請時に軽い気持ちで不正に手を染めることは、将来の大きなリスクを背負うことにつながります。
刑事罰や信用失墜
不正受給は詐欺罪や補助金適正化法違反として、刑事罰の対象になる場合があります。最大で5年以下の懲役や100万円以下の罰金といった重い罰則が科される可能性があります。さらに問題なのは、事業者名や所在地が公表されるなど社会的信用を大きく損なうことです。取引先や金融機関からの信用を失えば、今後の融資や契約にも悪影響を与え、経営そのものを揺るがしかねません。
申請停止や監査リスク
不正受給が確認されると、今後数年間は補助金や助成金の申請ができなくなります。事業を成長させるための公的な支援を利用できないことは、大きなハンデになります。さらに、一度不正が疑われると他の補助金の申請内容も徹底的に調査されます。過去の帳簿や契約書も含めて詳細な監査を受けるリスクが高まり、別の不正が見つかれば更なる返還や処分を受ける恐れがあります。日頃から正しい情報を残し、適正な管理をすることが重要です。
不正受給を防ぐ5つの具体的な対策
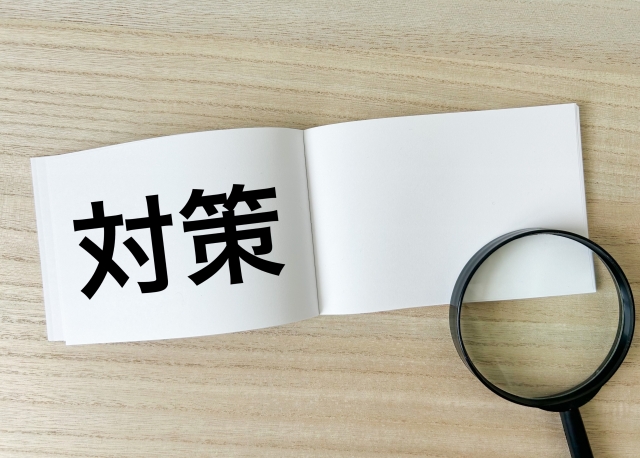
補助金制度の正しい理解
補助金を安全に活用するためには、まず制度の内容を正しく理解することが大切です。「自己負担ゼロ」「全額キャッシュバック」という誘い文句に流されず、公的制度の目的や仕組みをしっかり把握しましょう。経営者自身がルールを知っておくことで、業者からの過剰な営業を見抜き、不正の誘いを断る判断力を持つことができます。
申請書類の適正管理
補助金申請に必要な書類は正確に整え、責任を持って管理する必要があります。申請内容を他人任せにしたり、IDやパスワードを渡して代行させるのは大きなリスクです。自分で申請内容を理解し、必要な情報を適切に記入することで、後のトラブルを防げます。経営者自身が「申請の中身を説明できる状態」にすることが重要です。
契約内容や支払いフローの透明化
補助金を活用する際は、購入契約や支払いの流れを明確にし、証拠をしっかり残すことが大切です。「後から返金します」といった条件をのんでしまうと、不正受給とみなされる可能性があります。支払った金額や契約内容を正確に記録し、説明責任を果たせるようにしておきましょう。疑わしい提案はきっぱり断る勇気も必要です。
導入実績の正確な証拠保管
導入したITツールや研修の実施状況は、証拠を残すことが欠かせません。研修を受けた日付、内容、参加者の記録など、具体的な証明を用意することで、監査が入っても正しく説明できます。後から「本当に使っているのか」と問われたときに、自信を持って資料を提示できるように準備しておくことが不正防止の大きなポイントです。
専門家・公的機関への相談
補助金の制度や申請方法が分からない場合は、専門家や公的な相談窓口を活用しましょう。商工会議所や中小企業支援センターなどは、中立的な立場で正しい情報を教えてくれます。怪しい業者に流される前に、信頼できる窓口に相談することで、安全に申請を進められます。経営者として自分の判断だけで進めるのではなく、専門家の意見を取り入れる姿勢も大切です。
まとめ|適正な補助金申請で経営を成長させるために

正しい情報収集の重要性
補助金を活用することで、接骨院や鍼灸院は設備の導入やサービス向上を実現できます。ただし、そのためには正しい情報を集め、制度を理解することが欠かせません。不正受給は「知らなかった」では許されず、重い返還や罰則が待っています。経営者として、甘い誘い文句や不透明な提案に流されないよう、日頃から情報収集を怠らず、信頼できる情報源を活用する姿勢が大切です。
持続的な院経営への第一歩
補助金は一時的な支援に過ぎませんが、適正に活用することで院の成長を加速させることができます。不正を避け、正しい申請を行うことは、患者さんやスタッフ、地域からの信頼を守ることにもつながります。持続的な経営を実現するためには、制度を活かす知識と、誠実な対応が不可欠です。自院の未来を守るために、今こそ適正な申請のあり方を見直し、安心して経営を続けられる土台を作りましょう。



