整骨院が小規模事業者補助金を活用する前に確認すべき「保険診療対象外」ルールとは
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
小規模事業者持続化補助金で整骨院が注意すべき「保険診療対象外」ルールとは
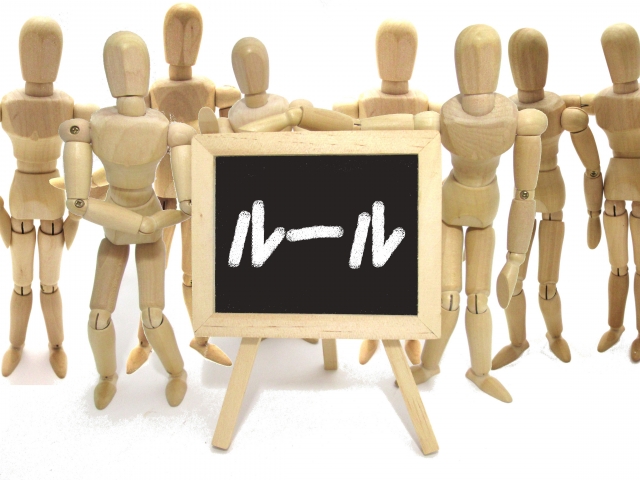
整骨院が補助金の対象になる基本条件
整骨院は小規模事業者に当たる場合、販路開拓や業務効率化を目的とした取組に対して支援を受けられます。ただし、対象はあくまで自費診療に関する取組に限られます。新しい自費メニューの導入、予約の導線改善、広告による集客など、患者さんが自由診療として支払うサービスに結び付く活動であることが前提です。ここで押さえたいのは、日常の保険診療に関わる支出は線引きの外に置かれるという点です。申請書の目的や費用の使途を、自費の売上拡大と結びつく形で明確に書けるかどうかが第一関門になります。
「保険診療」と「自費診療」の違いを正しく理解しよう
保険診療は公的保険のルールに基づく施術で、報酬は国が定める点数に沿って支払われます。一方で自費診療は施術者が価格や内容を自由に設計でき、体質改善プログラムや美容メニュー、パフォーマンス向上のためのコンディショニングなどが該当します。補助金は、市場開拓や収益性の向上を狙う活動を後押しする制度です。その目的に照らすと、保険の枠で提供する施術や、それを支える道具・消耗品・告知は公費との二重支援になり得るため対象外となります。逆に言えば、自費メニューの企画、販売ページの整備、予約導線の最適化などは制度の趣旨に合致しやすい領域です。
補助金申請でよくある誤解と申請ミスの原因
よく見かけるのは、保険施術にも使う汎用機器や院内備品を「自費の集客にも役立つ」と広く説明してしまうケースです。用途が保険と自費で混在すると、審査では保険寄りの利用と判断されやすく、対象外と見なされます。また、広告でも「交通事故・各種保険取扱い」を前面に掲げる内容は補助対象になりません。申請書では、対象者・提供価値・料金・提供手順を自費メニュー単位で具体化し、費用のひも付けを一点に絞ることが重要です。実施体制やKPIも自費売上や新規の自費患者獲得に直結する指標で整えると、目的の一貫性が伝わりやすくなります。
なぜ保険診療に関する経費は補助金の対象外になるのか

二重補助を防ぐための制度的な背景
小規模事業者持続化補助金は、事業者が自らの努力で販路を広げたり、経営を改善したりするための支援金です。一方、保険診療は国が定めた制度のもとで、診療報酬という形で公的な支援をすでに受けています。
この2つの支援が重なってしまうと「二重補助」となり、税金の公平な利用という観点から問題になります。そのため、保険診療に関わる機器購入や広告費などは補助対象から除外されているのです。制度の意図を理解したうえで、補助金の目的に合う活動を選ぶことが、審査で不利にならない第一歩といえるでしょう。
国からの診療報酬と補助金の関係
整骨院が行う保険診療では、施術内容ごとに国の定めた点数に基づいて診療報酬が支払われます。つまり、保険施術に使う設備や材料はすでにこの報酬の中で賄われており、別途補助金を充てるのは制度上の重複になります。
補助金は、事業者の「自主的な経営努力」を支えるためのものです。そのため、国の制度に守られている保険部分ではなく、自らの工夫やサービス設計によって新しい市場を切り開く「自費診療」領域こそが支援対象となります。この考え方を押さえておくと、申請の方向性がブレずに済みます。
審査で否認される主なケースとは
審査で否認されるケースの多くは、「保険診療の延長」と判断される内容です。たとえば、保険施術で使う低周波治療器の更新を目的とした申請や、保険施術の患者向けに作成する院内ポスター・看板などは、補助対象になりません。また、「保険も自費もどちらでも使う」と曖昧な説明をすると、審査側は保険用途が含まれると判断しやすくなります。
逆に、自費診療メニューの強化を目的とし、そのための専用機器や広告施策として明確に位置づけられていれば、採択される可能性は高まります。審査では「支出がどんな価値を生むのか」「保険制度と無関係であるか」を明快に示すことが求められるのです。
補助金の対象となる「自費診療」関連の取り組みとは

自費メニュー導入・強化のための投資例
整骨院が小規模事業者持続化補助金を有効に活用するためには、「自費診療」の領域でどのような取り組みが補助対象になるのかを明確に理解しておく必要があります。
たとえば、自費メニューとして姿勢矯正、産後骨盤ケア、美容鍼、EMSトレーニング、パフォーマンス向上コンディショニングなどを導入する場合、その準備に必要な設備導入や技術研修費用が対象となります。さらに、既存メニューの価値を高めるためのサービス設計やパッケージ化の費用も対象になることがあります。
重要なのは、患者の自由意志によって選ばれる自費施術を通じて、新しい収益源を生み出すことです。単なる備品購入ではなく、経営上の「売上拡大のストーリー」を描けるかどうかが評価の分かれ目です。
集客・販路開拓につながる取り組み
自費診療の拡大には、新しい顧客との接点をつくる仕組みが欠かせません。ホームページの改善やSNS広告の運用、Googleビジネスプロフィールの最適化など、患者が来院前にサービス内容を理解できる導線整備は補助金の対象になります。
また、リピーター育成のための予約システム導入、LINE公式アカウントを使った再来促進、口コミ獲得施策なども、業務効率化と販路拡大の両面で評価されやすい分野です。審査の際には、「集客 → 予約 → 再来」という流れの中でどの部分を改善するかを明確に示すことがポイントになります。自費施術の利用者が増える仕組みとして説明できれば、説得力が高まります。
設備導入や広告宣伝で補助対象となるケース
チラシ・ホームページ制作などの広告活動
チラシ配布やホームページの制作費用は、内容が自費施術に関するものであれば補助対象に含まれます。ここで重要なのは、広告の目的を「保険施術の告知」ではなく「自費メニューの魅力訴求」として明確にすることです。自費メニュー専用ページの作成や、ビフォーアフターの紹介なども有効です。患者が「自分に必要な施術だ」と感じられる具体的な情報を盛り込むことで、審査側も経費の妥当性を判断しやすくなります。
自費治療向けの新機器導入やサービス開発
自費診療に特化した治療機器の導入も補助対象になります。たとえば、美容鍼専用の微弱電流装置や、筋肉の深層部にアプローチするEMS機器、最新のハイボルテージ機器などは該当します。さらに、リラクゼーションやパフォーマンスアップなどの新しい分野を切り拓くためのサービス開発も認められることがあります。
ただし、購入理由や用途が「保険診療でも使用する」となると対象外になります。導入する機器やサービスが、自費施術にどのように貢献するのかを具体的に説明できるよう準備しておくことが大切です。
申請前に確認しておきたい対象外経費と注意点

補助金対象外となる代表的な経費
整骨院が補助金を申請する際に最も注意すべき点は、「対象外経費」をしっかり把握しておくことです。たとえば、日常的に保険診療で使用する治療機器や電療装置、保険施術のためのベッドや備品などはすべて対象外となります。これらは国の診療報酬の中で既に補助されているため、補助金の趣旨と重なってしまうからです。
また、家賃や光熱費、給与、仕入れなど、通常の運営経費も対象外です。さらに、保険施術に関する宣伝や「交通事故・各種保険取扱い」といった表記を含む広告も認められません。補助金は「経営の発展」を目的とするため、日常の維持費や制度内の活動とは明確に線を引く必要があります。
他制度との併用や重複申請の注意点
整骨院は他の公的支援制度も活用できる場合がありますが、複数の補助金・助成金を同一の経費に使うことはできません。これを「重複補助」といい、発覚すると返還の対象になります。たとえば、業務改善助成金で購入した機器を同じ名目で持続化補助金に申請することは不正と見なされます。
また、地方自治体独自の補助制度を併用する場合も、対象経費が重ならないよう注意が必要です。申請前に「どの制度の、どの経費に充てるか」を明確に整理しておくことで、審査でのトラブルや後の返還リスクを防ぐことができます。会計処理を分け、証憑類を丁寧に保管しておくことも重要な準備の一つです。
開業前・医療法人運営の場合の申請制限
小規模事業者持続化補助金は「すでに事業を行っている小規模事業者」が対象です。そのため、開業届を提出する前の準備段階や、まだ営業実績のない状態では申請できません。開業予定の整骨院が広告費や設備導入を計画していても、開業前に契約・支払いを行った場合は補助対象外になります。
さらに、整骨院が医療法人として運営されている場合も、営利法人や個人事業主ではないため制度の対象外です。補助金は中小企業や個人事業主の経営基盤強化を目的としているため、医療法人は「非対象事業者」に分類されます。
このような制度的制限を把握しておかないと、せっかくの申請書が形式上の不備で却下される可能性があります。申請前には、必ず自身の経営形態と開業日、事業内容を整理し、要件を満たしているかを確認しておくことが大切です。
まとめ:保険診療対象外ルールを理解し、補助金を賢く活用しよう

補助対象を見極めてムダのない申請を
小規模事業者持続化補助金を上手に活用するためには、「保険診療に関わる経費は対象外である」という原則を正確に理解することが欠かせません。補助対象とならない経費に無理に当てはめようとすると、審査で不備を指摘されたり、不採択となってしまうこともあります。
補助金の目的は、あくまで新しい顧客を獲得し、自院の収益基盤を強化することです。自費診療の拡大や業務の効率化など、経営発展につながる部分に焦点を合わせ、筋の通った申請内容に仕上げることが成功への近道です。
「自費診療への投資」が整骨院経営を強くする理由
保険制度に依存した経営では、診療報酬の改定や制度変更に大きく左右されてしまいます。そこで、自費診療を強化し、独自のサービスを育てることが安定した経営基盤づくりにつながります。補助金を活用して、自費メニューの導入や新しい機器の導入、広告戦略の見直しなどを行えば、保険制度に頼らない新しい収益源を確立することができます。
「自費施術を成長エンジンに変える」ことこそ、整骨院が補助金を最大限に活かすための本質的な方向性といえるでしょう。
専門家に相談しながら確実な申請を目指そう
補助金制度は年によって要件や評価基準が変わることがあり、整骨院経営者だけで判断するのは難しい部分もあります。商工会議所や中小企業診断士、行政書士などの専門家に相談することで、書類の整合性や採択率を高めるサポートを受けることができます。
特に、保険診療と自費診療の線引きや経費の使途説明は慎重さが求められるため、専門家のチェックを経て申請書を完成させるのが安心です。正しい理解と準備をもって臨めば、補助金は整骨院経営を次のステージへ引き上げる力強い支援となるでしょう。
emioでは、事前相談も受け付けております。公式LINEよりお気軽にご相談下さい。



