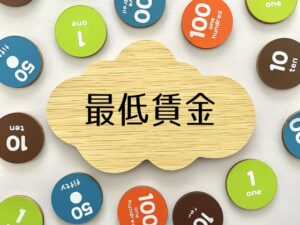接骨院・鍼灸院向け就業規則の作り方|5つの必須項目と作成手順
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
就業規則とは?接骨院・鍼灸院でも必要な理由
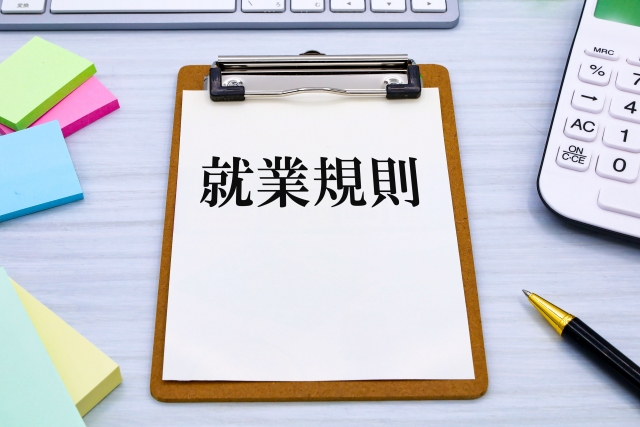
就業規則の基本的な定義と役割
就業規則とは、職場で働く人たちが守るべきルールをまとめた文書です。勤務時間や給与の支払い方法、休日や休暇の取り方など、働く上での基本的な取り決めが記載されています。これは会社と従業員の間でトラブルを防ぐために非常に重要な役割を果たします。
たとえば、「何時から仕事が始まるのか」「遅刻や欠勤はどう扱われるのか」など、曖昧なままでは不満や誤解が生まれがちです。就業規則を整備しておくことで、従業員にも安心感が生まれ、経営者としても説明責任を果たすことができます。
接骨院・鍼灸院でも義務となるケース
個人経営であっても、接骨院や鍼灸院に常時10人以上の従業員がいる場合は、労働基準法により就業規則の作成と届け出が義務となります。ここでの「10人以上」とは、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトも含めた人数です。
労働基準法第89条の概要
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業場には、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出るよう定められています。この規定に違反すると、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。
常時10人以上雇用の判断基準
「常時」という言葉に迷う方も多いですが、これは1日ごとの状況ではなく、継続的に10人以上の従業員が働いている状態を指します。たとえば、日によって人員に波があっても、平均して10人以上が働いている場合は対象になります。短時間労働者や試用期間中の人も原則として含まれます。
就業規則に記載すべき必須項目とは
絶対的必要記載事項とは
接骨院や鍼灸院に限らず、すべての事業所で就業規則に必ず書かなければならない内容があります。これを「絶対的必要記載事項」といいます。まず重要なのが労働時間に関することです。始業と終業の時刻、休憩時間の取り方、休日の設定などがここに含まれます。従業員がいつ働き、いつ休めるのかを明確にしておくことは、勤務のトラブルを避ける第一歩です。
次に、賃金に関する事項も記載が必要です。たとえば給与の金額、計算方法、支払い方法、締日や支払日などが該当します。これらを曖昧にしていると「約束と違う」といった不満が出てしまいます。あらかじめルールを文書で示しておくことで、信頼性が高まります。
そしてもう一つの重要なポイントが退職に関する事項です。自分から辞めるとき、あるいは解雇される場合の手続きや条件について記載しておくことで、離職時のトラブルを未然に防ぐことができます。
労働時間・休憩・休日
具体的には「午前9時始業・午後6時終業、12時から1時間休憩」などの形で記載します。週何日勤務するのか、定休日は何曜日かなど、スタッフ全員が把握できるように明文化することが重要です。接骨院や鍼灸院では土日営業のところも多いため、曜日ごとの勤務体制も細かく記載しておくと混乱を防げます。
賃金の支払い方法・締日・支払日
賃金は「毎月末締め、翌月10日払い。銀行振込にて支払う」といったように、誰が見てもわかりやすく示すことがポイントです。歩合制やインセンティブ制度がある場合は、その条件についても記載しておくと公平性が保たれます。
退職・解雇の条件
退職の申し出は何日前までに必要か、解雇の事由にはどのようなものがあるかを明確にしましょう。たとえば「業務命令に繰り返し違反した場合」など、客観的に判断できる内容にしておくことで、感情的なトラブルを防ぐことができます。

相対的必要記載事項とは
相対的必要記載事項とは、制度として設ける場合には必ず記載しなければならない内容です。たとえば退職金の制度がある場合、その支給条件や計算方法を就業規則に明記する必要があります。また、表彰や制裁、教育訓練、福利厚生なども同様です。
退職金・表彰・制裁など
退職金制度を導入している場合は「勤続5年以上の職員に支給する」「金額は月給の〇ヶ月分」といったように具体的な内容を記載しましょう。また、表彰制度や懲戒処分のルールについても、対象となる行為や手続きの流れを簡潔に記載すると公平性が担保されます。
任意記載事項の例
任意記載事項とは、記載してもしなくてもよい内容ですが、職場運営の明確化のために役立ちます。たとえば制服の貸与、院内ルール、院外研修の扱い、SNSの使用に関する注意点など、職場ごとに独自の事情に合わせて記載できます。
制服貸与や福利厚生の内容など
接骨院や鍼灸院では、施術時に制服を着用するケースが多いため、その貸与ルールやクリーニングの取り扱いについても明記しておくとよいでしょう。また、インフルエンザ予防接種の補助、スポーツジム利用の福利厚生などがある場合も、就業規則に記載しておくことで新入職員にも分かりやすく伝えられます。
就業規則の作成手順|接骨院・鍼灸院に合った進め方
労働者代表の選出と意見聴取
就業規則を作成するときには、経営者だけの判断で内容を決めてはいけません。従業員の意見を聞くことが法律で求められています。具体的には、従業員の中から「労働者代表」を選び、その人に就業規則の内容を確認してもらいます。この労働者代表は、上司や経営層ではなく、現場のスタッフから公平に選ばれる必要があります。
意見聴取といっても、内容に同意してもらう必要はありません。ただし、就業規則案を提示し、意見がある場合は記録に残す必要があります。これによって、労使間の透明性が保たれ、公平なルールづくりが実現できます。
就業規則の原案作成時の注意点
就業規則の原案を作る際は、テンプレートをそのまま使うのではなく、自院の実情に合わせてカスタマイズすることが大切です。たとえば診療時間が夜間に及ぶ場合や、訪問施術を行っている場合などは、それに応じた勤務時間の記載が求められます。
また、職場内でトラブルが起こりやすい項目(遅刻・早退・私用スマホの使用など)は、具体的にルールを定めておくことで、あとから揉めるのを防ぐことができます。
言い回しはできるだけ簡潔で、誰が読んでも同じように理解できる表現にしましょう。難しい表現や曖昧な言葉を使うと、かえって混乱を招く可能性があります。
院の実情に合わせたカスタマイズ方法
接骨院や鍼灸院は、一般企業とは異なる業態です。そのため、一般的な就業規則だけではカバーしきれない点もあります。たとえば施術ベッドの清掃ルール、患者情報の取り扱い、急患対応時の勤務変更など、医療類似業務ならではの場面を想定して記載を加えると実務に即した内容になります。
また、スタッフが資格を有しているかどうかでも職務内容は異なるため、業務内容に応じてルールを明確に分けるのも有効です。たとえば、受付スタッフと施術者で適用されるルールが異なる場合は、それぞれに対応する章を設けておくと、誤解を防ぐことができます。
労働基準監督署への届け出方法と必要書類
提出が必要な書類一覧
就業規則を作成しただけでは終わりではありません。常時10人以上のスタッフを雇用している接骨院・鍼灸院では、労働基準監督署への届け出が義務付けられています。届け出に必要な書類は主に2つあります。
ひとつ目は、完成した就業規則本体です。これは紙でも電子データでも構いませんが、内容に漏れがないかを確認してから提出することが大切です。ふたつ目は、従業員の代表者から取得する「意見書」です。この意見書は、就業規則に対して意見を述べた証拠となる書類で、必ず添付しなければいけません。
提出先は、接骨院や鍼灸院の所在地を管轄する労働基準監督署です。別の場所に分院がある場合でも、スタッフの多くが勤務する本院の所在地が基準になります。
就業規則本体
この書類には、これまで解説してきた5つの記載項目がすべて含まれている必要があります。中でも労働時間や賃金、退職に関するルールが明確でなければ受理されないこともあるため、丁寧に確認しましょう。フォーマットに決まりはありませんが、表紙と目次をつけておくとより親切です。
意見書の添付について
意見書には、労働者代表の氏名と意見の内容、日付が記載されている必要があります。内容は「賛成」や「反対」に関わらず、意見そのものが記録されていれば問題ありません。この意見書を提出し忘れると、届け出が無効になるため注意が必要です。
労働基準監督署への提出手順
提出の手順は比較的シンプルです。完成した就業規則と意見書をそろえたら、管轄の労働基準監督署に持参するか、郵送、または電子申請システム「e-Gov(イーガブ)」を利用して提出することができます。最近では電子申請を活用するケースも増えており、忙しい院長にとっては便利な方法です。
担当者によるチェックが行われたあと、特に問題がなければ受理されます。内容に不備がある場合は修正を求められることもありますが、その際もアドバイスをもとに見直すことでスムーズに対応できます。
届け出後の流れと審査のポイント
就業規則を届け出たあとは、内容に問題がなければそのまま受理され、院内で正式な規則として運用できるようになります。労働基準監督署から特別な通知は届きませんが、受理印のある控えを手元に保管しておくことが重要です。
また、審査時にチェックされやすいポイントとしては、労働時間と賃金、休暇の記載が現実的であるか、そして解雇条件が不当でないかどうかなどが挙げられます。形式だけ整っていても、実態とかけ離れていると修正を求められる場合があります。院の現場に即した内容であることが大切です。

就業規則の見直しや変更時に注意すべきこと
就業環境や制度変更に応じた改定の必要性
一度作成した就業規則も、そのままで永遠に使えるわけではありません。働き方や法制度が変われば、それに合わせて規則も見直す必要があります。たとえば、営業時間の変更や新しい勤務形態の導入、育児休業制度の拡充などがあったときには、その内容を規則に反映させることが求められます。
接骨院や鍼灸院でも、業務の多様化により以前とは異なるルールが必要になる場面が増えています。新たな人材を雇う際やスタッフの働き方に変化があったときは、その都度、就業規則が現状に合っているかを見直す習慣を持つことが重要です。
変更時にも必要な意見聴取と届け出
就業規則の内容を変更する場合も、最初に作成したときと同じように、労働者代表から意見を聴取する必要があります。形式だけでなく、実際に新しいルールを共有し、意見をもらった記録を「意見書」として残すことが求められます。
また、変更内容が従業員にとって不利益となる場合は、特に注意が必要です。たとえば、これまでよりも勤務時間が長くなるような改定は、一方的に進めてはいけません。従業員の納得と理解を得るプロセスが大切です。
変更後の就業規則は、再び労働基準監督署に届け出る必要があります。小さな修正であっても、届け出を怠ると、後々のトラブルにつながる可能性があるため、必ず所定の手続きを行いましょう。
誤解を生まないための記載の工夫
就業規則は、法律文書ではありますが、読むのは現場で働くスタッフです。専門的な用語や難しい言い回しはできるだけ避け、シンプルで分かりやすい表現にすることが大切です。誤解を招くような曖昧な表現は、職場内の混乱やトラブルの原因になります。
たとえば「勤務態度が悪い場合は処分する」といった抽象的な表現ではなく、「業務命令に対して正当な理由なく従わない場合は、注意・指導の対象とする」といったように、具体的な行動を示すことで、従業員も納得しやすくなります。
また、就業規則は一度作ったら終わりではなく、定期的な見直しを前提にした文書であることを念頭に置きましょう。院の成長に合わせて、ルールも柔軟に進化させていくことが、働きやすい職場づくりに直結します。
就業規則を周知・活用するメリットと現場での伝え方
周知義務の内容と具体的方法
就業規則は作成して届け出を済ませたら終わり、というわけではありません。労働基準法では、従業員への「周知」が義務とされています。つまり、職場の全員が就業規則の内容を確認できる状態をつくることが必要です。
具体的な方法としては、紙の就業規則を従業員一人ひとりに配布する、事務所の見やすい場所に掲示する、あるいは院内の共有パソコンなどで常に確認できるように設置するなどが挙げられます。いずれの方法でも、従業員が容易にアクセスできるようにしておくことが大切です。
配布した場合には「受領確認書」にサインをもらうと、周知が完了した証明になります。これにより、万が一トラブルが起きた際にも、「就業規則に基づいて対応している」と説明しやすくなります。
周知がもたらすトラブル防止効果
就業規則を周知することの最大の効果は、従業員との間に無用な誤解や認識のズレを生じさせないことにあります。「知らなかった」「聞いていない」といった言葉は、職場でのトラブルを引き起こす原因になりがちです。
たとえば、遅刻や早退の扱い、休暇の取得ルール、服装や髪型に関する基準など、細かなルールであっても事前に明示されていれば、不満や対立を未然に防ぐことができます。従業員にとっても、自分の働き方の基準がはっきりすることで安心して業務に集中できるようになります。
就業規則を現場で活かすための工夫
せっかく整備した就業規則も、ただ存在するだけでは意味がありません。現場で活用され、自然と守られるルールになるためには、日々のコミュニケーションが重要です。たとえば、朝礼やミーティングで定期的に内容を振り返ったり、新しく入ったスタッフには研修の中でしっかりと説明したりすることが効果的です。
また、就業規則の内容が現場の実態と乖離していないか、スタッフの声に耳を傾けながら見直していくことも大切です。従業員が「この規則は自分たちのためにある」と感じることができれば、自然と守る意識も高まります。
特に接骨院・鍼灸院のように少人数で運営する職場では、規則の内容を共有する場を積極的につくることで、より良いチームワークと信頼関係を育むことができるでしょう。