補助金対策に必須!「付加価値額・給与支給総額の年平均成長率」の基礎知識と3つの実務ポイント
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
補助金申請に求められる「年平均成長率」とは?基本用語を整理

年平均成長率とは?なぜ補助金で問われるのか
補助金の申請において、「年平均成長率」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。これは、ある数値が年々どのくらいの割合で成長しているかを、平均して示す指標です。特に「付加価値額の年平均成長率」や「給与支給総額の年平均成長率」は、補助金の審査で採択されるかどうかを左右する大事な判断材料となります。
なぜこのような指標が求められるのでしょうか?それは、国や自治体が補助金を通じて「成長性のある事業者」を支援したいと考えているからです。つまり、成長している企業かどうかを見極めるために、数値的な裏付けが必要になるのです。
「成長率」の判断基準と目安数値とは
成長率と聞くと、何%であれば良いのかが気になるところです。例えば「ものづくり補助金」などの制度では、給与支給総額の年平均成長率が、地域の最低賃金の上昇率と同等以上であることが求められるケースもあります。一般的には、年平均3%以上の成長率が一つの目安とされています。
ただし、業種や事業規模によっては、この数値がやや高いと感じる場合もあるかもしれません。大切なのは、提出する計画書において、なぜその成長率を達成できるのかを説明できる根拠を持っておくことです。
付加価値額と給与支給総額、それぞれの成長率の意味と違い

付加価値額の年平均成長率とは
付加価値額の定義と計算式
「付加価値額」とは、企業が事業を通じて新たに生み出した価値の合計を表すものです。具体的には、営業活動によって得られた利益に加え、従業員に支払った給与、設備などの減価償却費を合計して算出されます。
計算式は次のとおりです。
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
この付加価値額を複数年にわたって比較し、毎年どれくらいのペースで増えているかを示すのが「年平均成長率」です。補助金制度ではこの成長率が、経営の持続性や成長性を判断する根拠として使われます。
成長率の目安と業種別傾向
付加価値額の年平均成長率には業種ごとにバラつきがありますが、全体の目安として年5%前後が中央値とされています。たとえば、ITや製造業などでは10%を超えることもありますが、接骨院や鍼灸院といったサービス業では3〜6%程度が現実的なラインです。
重要なのは、過去の実績と今後の見通しを合わせて示し、無理のない範囲で着実な成長を数字で裏付けることです。過大な数値を盛り込むと、審査で信頼性を疑われるリスクがあります。
給与支給総額の年平均成長率とは
計算に含める費用項目と注意点
「給与支給総額」は、従業員に支払われる給与・賞与・手当などすべての人件費を合計したものです。これを年ごとに集計し、どのくらい増加しているかを計算することで、給与支給総額の年平均成長率が求められます。
ただし、注意点があります。それは、外部委託費や個人事業主への報酬などは含まれないという点です。また、給与台帳など信頼できる資料をもとに数字を算出する必要があります。補助金申請では証拠書類の整備も重要な審査ポイントになります。
最低賃金との関係性
近年、最低賃金は毎年のように引き上げられています。そのため、給与支給総額の成長率もそれに合わせて一定以上でなければ「従業員の待遇改善が不十分」と判断される可能性があります。
たとえば、直近5年間で東京都の最低賃金は平均で年3%前後の上昇を記録しています。つまり、それ以上の成長率があれば、補助金要件をクリアする可能性が高くなるということです。
成長率の計算はこうする!補助金申請で使える具体例付き

成長率の基本計算式
年平均成長率の計算は、一見むずかしく感じるかもしれませんが、実はひとつの公式に当てはめるだけで簡単に求めることができます。
基本の計算式は次のとおりです。
年平均成長率(CAGR)=(最終年の数値 ÷ 初年度の数値)^(1/n) − 1
ここで「n」は年数を意味します。つまり、初年度から最終年までにどのくらい成長したかを、年平均でどのくらいの割合になるかに置き換えたものです。
計算に必要なデータの集め方
成長率を正確に出すためには、過去数年分の数値データが必要になります。具体的には以下のような情報を整理しましょう。
- 付加価値額:営業利益、人件費、減価償却費の合計
- 給与支給総額:給与、賞与、手当などの総額
これらのデータは、決算書や給与台帳、固定資産台帳などから取得できます。年度ごとに正確に整理しておくことで、計算だけでなく、補助金申請時の根拠資料としても活用できます。
また、過去3年分を使う場合には、2022年度・2023年度・2024年度の数値を用意し、それぞれの項目について数値を並べておくと計算がスムーズです。
実際のシミュレーション例で確認
それでは、簡単な例で実際に計算してみましょう。
たとえば、ある接骨院の付加価値額が以下のように推移していたとします。
- 2021年:800万円
- 2024年:1,000万円
この場合の年平均成長率は以下のように計算します。
CAGR=(1,000 ÷ 800)^(1/3) − 1 ≒ 7.7%
つまり、年平均で約7.7%ずつ付加価値額が成長していることになります。
同様に、給与支給総額も計算できます。仮に2021年が600万円、2024年が675万円の場合、
CAGR=(675 ÷ 600)^(1/3) − 1 ≒ 4%
このように、実際に数字をあてはめてみることで、申請条件を満たせるかどうかの判断が可能になります。計算結果が補助金の基準値(例えば3%以上)を超えているかを確認し、必要に応じて改善計画を盛り込むことが重要です。
採択を左右する!申請前に押さえるべき3つの実務対策

① 正確な数値管理と記録の徹底
補助金申請では、「数字」がすべての土台になります。特に付加価値額や給与支給総額の成長率を証明するには、過去の実績を裏付ける資料が必要です。
たとえば、決算書・給与台帳・損益計算書などの記録が正確に保管されていない場合、成長率の根拠を示すことができず、申請が通らないリスクがあります。逆に、信頼性のある資料で数値が明確に確認できれば、審査担当者への印象は格段に良くなります。
普段からデータを年度ごとにまとめ、紙ベースだけでなくデジタルでも整理しておくことで、急な申請にもスムーズに対応できるようになります。
② 要件に合わせた事業計画の見直し
計算した成長率が補助金の要件を下回っている場合、そのままでは採択される可能性は低くなります。そのようなときは、提出する事業計画を見直すことが重要です。
たとえば、今後導入する設備が売上アップにどう結びつくか、人件費の増加がどのように従業員の生産性向上につながるかなど、成長率を高めるストーリーを計画書に盛り込むことが必要です。
「どうして成長するのか?」という問いに数字とロジックで答えられるようにすることで、説得力のある申請になります。
③ 成長率を高めるための施策実行
成長率は、過去の数字だけでなく、これからの取り組み次第でも変えていくことができます。
たとえば、以下のような取り組みが効果的です。
- 施術以外の自由診療メニューを強化して売上を増やす
- スタッフの働き方を見直し、生産性を向上させる
- SNSやGoogleビジネスプロフィールを活用し集客力を上げる
こうした日々の積み重ねが、1年後・3年後の成長率として数字に表れてきます。単に計算結果を整えるだけでなく、実際に改善行動を起こすことが、採択を勝ち取るための近道です。
まとめ:成長率を見直して、補助金活用に強い経営体質へ
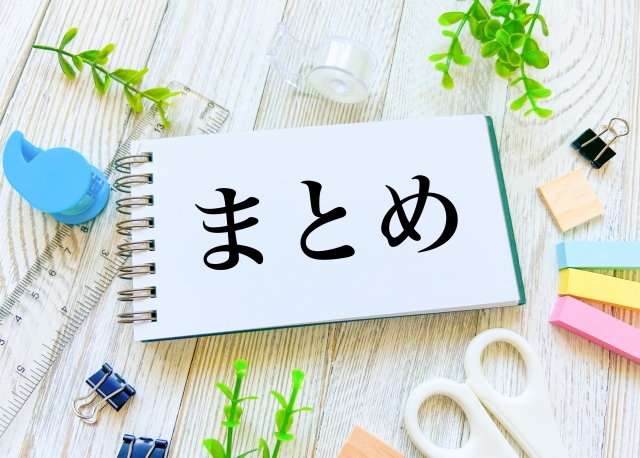
成長率を知ることは経営改善の第一歩
「付加価値額」や「給与支給総額」の年平均成長率という言葉は、難しそうに聞こえるかもしれませんが、その本質は“自院がどれだけ前進しているか”を表すシンプルな指標です。これらの数値を見直すことで、経営の現状と将来の課題がはっきりと見えてきます。
数字を正しく理解することは、単に補助金のためだけでなく、長期的な経営改善やスタッフの働きやすさ向上にもつながります。
今後の補助金活用に向けて準備すべきこと
補助金を有効に活用するためには、普段からの準備が何より重要です。成長率を意識した経営と数値の把握を習慣化することで、いざというときの申請に自信をもって臨めるようになります。
今できる第一歩として、まずは過去3年分の付加価値額と給与支給総額を整理し、実際に年平均成長率を計算してみましょう。もし数値が目標に届いていなければ、次にどう改善するかを考える絶好の機会になります。
制度に振り回されるのではなく、数字を味方につけて補助金を活かす。その姿勢こそが、経営の安定と成長につながる確かな一歩となります。



