接骨院オーナー必見!今さら聞けないM&Aの意味と仕組みをわかりやすく解説
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
M&Aとは?接骨院オーナーが知っておくべき基本の意味

M&Aは「合併と買収」を指す言葉ですが、接骨院の現場ではもう少し身近な意味を持ちます。オーナーが築いてきた院を、別の個人や会社へ引き継ぐ仕組みの総称だと捉えると理解が早く、看板やスタッフ、患者さんとの関係、ノウハウや設備など、院の価値そのものを次の担い手へ渡すための方法です。廃業か継続かの二択ではなく、第三の選択肢をつくる考え方であり、今の働き方や将来設計に合わせて柔軟に出口や成長の道を選べる点が特徴と言えます。
M&Aの基本的な定義と意味
定義としては、複数の組織が一つになる合併、片方がもう片方を取り込む買収、院の一部や店舗単位を受け渡す事業譲渡などを含みます。接骨院の場合は、法人の枠組みよりも「店舗と運営の引き継ぎ」が中心になりやすく、患者さんが通う場所とサービスの連続性が重視されます。経営者が交代しても、施術品質と通いやすさが保たれれば、患者さんにとっては“いつもの院”の延長として受け止められます。この連続性を保つ計画が、M&Aの成否を左右します。
中小規模の接骨院にも関係する理由
院長の高齢化や人手不足、家賃や人件費の上昇など、個院だけでは吸収しにくい変化が続いています。新規出店で一から患者さんを集めるより、既存の院を引き継いだほうが、通院実績やスタッフの経験をそのまま活かせます。売り手にとっては廃業よりも患者さんと従業員を守りやすく、買い手にとっては立ち上げコストと時間を抑えられるため、双方に合理性があります。だからこそ小規模でも対象になり、地域単位での承継や統合が現実的な選択肢になります。
事業承継とM&Aの違いを理解しよう
事業承継は、本来オーナーの後継ぎに事業を引き継ぐ広い概念で、親族や社員、外部の第三者へ継ぐ方法を含みます。第三者に引き継ぐときに用いる具体的な手段の一つがM&Aです。つまり、承継という目的に対して、M&Aはその達成手段のセットだと考えると整理できます。接骨院では、親族や社員に適任者がいない場合でも、第三者への譲渡を通じて理念や施術方針を守りながら継続できる可能性が広がります。価格や条件の交渉だけでなく、理念の共有と引き継ぎ計画をどう設計するかが鍵になります。
なぜ今、接骨院業界でM&Aが注目されているのか
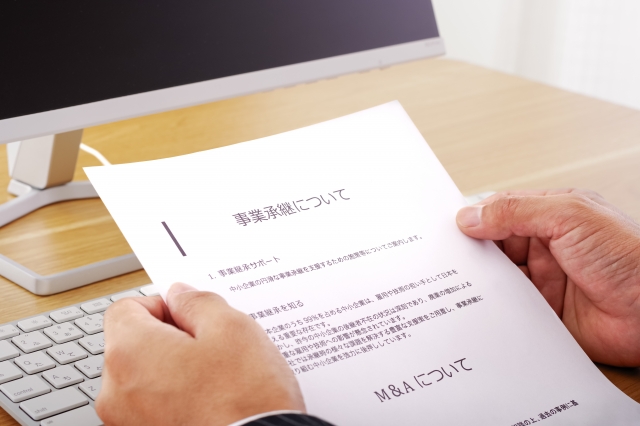
近年、接骨院業界で「M&A(事業の引き継ぎや買収)」が増えている背景には、業界全体が直面している構造的な課題があります。個人経営が多いこの分野では、院長の高齢化や人手不足、そして保険制度の見直しなどが経営を圧迫しています。こうした状況のなかで、事業を閉じるのではなく“引き継ぐ”という選択が現実的な解決策として注目されています。M&Aを活用することで、自院のノウハウや患者さんとの信頼関係を次世代に残すことができるため、「廃業」から「継続」へと発想を転換する動きが広がっているのです。
接骨院業界を取り巻く環境変化
接骨院や整骨院の数は全国的に増加し続け、競争は年々激しくなっています。さらに、新型コロナの影響で患者の来院頻度が減り、オンライン予約やSNS集客などデジタル対応の遅れが課題になる院も少なくありません。保険制度の厳格化により施術内容が制限され、自由診療や美容・リハビリ分野へ広げる動きも進んでいます。これらの変化のなかで、単独での経営には限界を感じる院長も多く、グループへの参加や譲渡による経営安定化が注目されるようになりました。
後継者不足と人手不足が引き起こす問題
地域密着型で運営されてきた接骨院の多くは、院長が現場の中心として長年支えてきました。しかし後継者がいないまま高齢を迎えるケースが増え、「閉院するしかない」と考える経営者も少なくありません。スタッフ確保も難しく、経験のある施術者を育てるには時間がかかります。M&Aは、こうした後継者問題を解決する有力な手段であり、雇用や患者サービスを守るための現実的な選択肢として支持されています。
買い手(大手・グループ企業)が増えている背景
買い手の側も、接骨院業界の安定した顧客基盤に魅力を感じています。リハビリ、美容、フィットネス、介護といった隣接分野と親和性が高く、事業拡大の一環として既存院を取り込む動きが強まっています。大手グループは資金力と経営ノウハウを持ち、設備更新や集客支援を通じて院の価値を高められるため、売り手・買い手双方にとって利益が生まれやすい構造です。こうした流れが、今後さらに接骨院業界でのM&Aを加速させる要因になっています。
M&Aの仕組みをわかりやすく解説|合併・買収・事業譲渡の違い

「M&A」という言葉を聞くと、大企業同士の買収劇を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、接骨院の場合はもっとシンプルで現実的な仕組みです。事業の一部や店舗を他のオーナーや法人に引き継ぐ形が一般的で、院の運営や患者との関係をそのまま維持しながら経営者だけが変わるイメージに近いでしょう。ここでは、M&Aの基本的な種類とそれぞれの特徴を整理し、接骨院オーナーが理解しやすい形で解説します。
合併と買収の基本構造
合併とは、2つ以上の事業体が1つにまとまることを意味します。たとえば、複数の接骨院が協力して「新しい法人」を立ち上げ、経営を一本化するケースです。これに対し、買収は片方がもう一方を取り込む形で、既存の法人や個人経営を買い取って自社のグループに加えます。接骨院業界では、後者の買収型が主流であり、経営の効率化や店舗数の拡大を狙う大手グループによって活発に行われています。買収といっても、経営権が変わるだけで院の名前やスタッフ、場所はそのままのことも多く、患者にとっての変化は最小限に抑えられるのが特徴です。
事業譲渡とは?中小院で最も多い形態
接骨院では、「事業譲渡」と呼ばれる形式が最も一般的です。これは、法人全体ではなく、院という“事業単位”を別の経営者へ引き渡す方法で、売り手・買い手双方に柔軟な調整が可能です。たとえば、ある地域で長年続く接骨院を若手の施術家が引き継ぎ、院の名前や設備、患者情報、従業員をそのまま引き継ぐ形です。こうした譲渡では、患者との信頼関係やスタッフの雇用を守りながら、スムーズに経営をバトンタッチできることが大きな利点です。一方で、契約内容や引き継ぎ範囲を明確にしないとトラブルのもとになるため、専門家の助言を受けながら進めることが重要になります。
売り手・買い手の流れと必要なステップ
M&Aの流れは大きく分けて、「準備 → 相手探し → 条件交渉 → 契約 → 引き継ぎ」という5段階です。最初に行うのは、自院の現状分析と価値の把握です。どのくらいの患者が通っているのか、どのような施術が強みか、地域での評判などを整理して、譲渡の目的を明確にします。次に、専門家やマッチングサイトを通じて買い手を探し、条件をすり合わせます。契約後は、スタッフや患者への引き継ぎ、経営体制の変更を丁寧に行うことで、トラブルを防ぎながらスムーズに移行できます。これらのステップを計画的に進めることが、成功するM&Aの第一歩となります。
接骨院がM&Aを行うメリットと注意点

接骨院がM&Aを行う目的は、「経営を手放すこと」ではなく、「院を未来につなぐこと」にあります。自分が築いた院を守りたい、スタッフの雇用を継続したい、患者との関係を絶やしたくない――こうした想いを叶えるために、M&Aは一つの有効な選択肢です。さらに、売り手と買い手の双方にとって明確な利点がありますが、その一方で注意すべきリスクも存在します。ここでは、それぞれの立場から見たメリットと注意点を詳しく整理していきましょう。
売り手側(院長・オーナー)のメリット
売り手にとっての最大のメリットは、引退や方向転換の際に「事業を閉じずに次の人へ託せる」ことです。これまで築いた院の信頼や患者を守りながら、経営を引き継げます。また、譲渡金によって老後資金や新たな挑戦の資金を確保できるのも大きな魅力です。さらに、自分が中心だった院運営を次の経営者に任せることで、スタッフのキャリアアップや組織の新陳代謝にもつながります。つまり、M&Aは“終わり”ではなく“新しいスタート”として、院の未来を前向きに引き継ぐ仕組みなのです。
買い手側(企業・グループ)のメリット
買い手にとってM&Aの魅力は、ゼロから新規出店するよりも短期間で地域に根ざした事業を展開できることです。既に患者基盤や評判を持つ接骨院を引き継ぐことで、集客や広告のコストを大幅に削減できます。また、経験豊富なスタッフをそのまま迎え入れられるため、教育コストも抑えられます。さらに、既存院の経営データや顧客情報をもとに、サービス改善や新メニュー開発にもつなげやすい点がメリットです。複数院を展開するグループにとっては、地域ネットワークの拡大やブランド力強化にも直結します。
契約・評価・引継ぎで注意すべきリスク
M&Aはメリットばかりではありません。契約条件の不備や認識のズレがあると、後々トラブルに発展するケースもあります。特に注意すべきは「譲渡範囲の明確化」と「評価額の妥当性」です。例えば、設備や患者データ、スタッフ雇用の扱いを曖昧にしたまま契約すると、引き継ぎ後の責任範囲で揉めることがあります。また、過去の保険請求や会計処理に不備があると、買い手が想定外のリスクを背負う可能性も。こうしたトラブルを防ぐには、専門家(M&A仲介会社、税理士、社労士など)を交えて契約内容を慎重に精査することが大切です。
まとめ|M&Aを正しく理解し、将来の経営判断に活かそう

接骨院にとってM&Aは、単に「売却」や「買収」といった経営戦略ではなく、未来へ院をつなぐための手段です。これまで積み上げてきた信頼関係、技術、人材を次の世代に引き継ぐことで、地域の患者さんにとっても安心できる継続的な治療環境を守ることができます。
M&Aは「事業をつなぐ選択肢」
M&Aという言葉には“経営の終わり”という印象を持つ人もいますが、実際には「事業の継続」こそがその目的です。院長が引退や方向転換を考える際に、閉院ではなく「引き継ぐ」という道を選べることで、これまで築いた努力が無駄にならず、患者やスタッフも安心して新しい体制を迎えられます。小さな院であっても、地域に根ざした信頼やブランド価値は確かな資産です。その価値を次へ渡すことこそが、M&Aの本質と言えるでしょう。
基本理解が未来の経営判断を支える
M&Aの仕組みを理解しておくことは、すぐに実行する予定がなくても大きな意味があります。今後、地域医療やリハビリ、美容などの隣接分野と連携が進むなかで、外部との提携や統合を検討する場面が増えるかもしれません。そのとき、M&Aの基本を知っているかどうかで判断の精度が大きく変わります。つまり、知識を持つこと自体が“経営のリスクヘッジ”になります。
次のステップ:専門家への相談と準備の重要性
実際にM&Aを検討する際は、信頼できる専門家へ相談することが第一歩です。院の財務状況や契約関係を整理し、どのような形で譲渡したいのか、どんな相手に引き継いでほしいのかを明確にしておくことが成功の鍵になります。M&Aは一度きりの大きな決断ですが、正しい知識と準備があれば、経営者にもスタッフにも、そして患者にもプラスの結果をもたらす選択となります。



