接骨院・鍼灸院が押さえておきたい!地域別最低賃金の決まり方と経営を守る3つのポイント
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
地域別最低賃金とは?基本の仕組みを解説
地域別最低賃金の定義と特徴
地域別最低賃金とは、都道府県ごとに設定された「労働者に支払う最低限の賃金水準」のことです。この制度は、地域ごとに物価や賃金水準、産業構造が異なることを考慮し、全国一律ではなく地域別に決められています。
この最低賃金は、アルバイトやパートを含めたすべての労働者に適用され、たとえ短時間勤務でも、最低賃金を下回る時給で雇うことは法律違反となります。また、月給制や日給制の社員についても、1時間あたりに換算した金額が最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。
地域別最低賃金は、労働者の生活を守るための制度であると同時に、企業側にとっては人件費の最低ラインを示す基準でもあります。そのため、最低賃金の改定は経営に直接影響を及ぼすことがある重要な要素といえるでしょう。

全国一律最低賃金との違い
最低賃金制度には大きく分けて2つのタイプがあります。ひとつがこの「地域別最低賃金」、もうひとつが「特定(産業別)最低賃金」です。
一方で、「全国一律最低賃金」という制度は実際には存在していません。政府が目安として「全国加重平均」を発表することがありますが、それはあくまで各都道府県が基準を決める際の参考値にすぎません。
実際には、東京や神奈川のような都市部では物価が高いため最低賃金も高めに設定され、地方ではそれに比べてやや低い水準にとどまっているのが現状です。このように、地域による経済状況を踏まえて柔軟に設定されるのが地域別最低賃金の特徴といえます。
適用される労働者と事業者の範囲
地域別最低賃金は、企業の規模や業種にかかわらず、その地域で働くすべての労働者に適用されます。パートタイム、アルバイト、契約社員、派遣社員、外国人労働者などもすべて含まれており、例外はほとんどありません。
また、事業主側にも規模の大小を問わず義務が発生します。中小企業だからといって適用が免除されるわけではなく、従業員を1人でも雇用していれば、最低賃金の順守が求められます。
注意すべき点は、たとえ労働者が合意していたとしても、最低賃金を下回る賃金で契約することは違法となる点です。違反が発覚した場合には、事業主に対して差額の支払い命令や是正勧告がなされることがあります。
地域別最低賃金はどうやって決まるのか?
中央最低賃金審議会と地方審議会の役割
地域別最低賃金の決定には、「中央最低賃金審議会」と「地方最低賃金審議会」という二つの組織が関わっています。
まず、厚生労働省に設置されている中央最低賃金審議会は、毎年夏ごろに「引き上げ額の目安」を全国に提示します。これは全国的な賃金状況や物価の動き、経済全体の成長率などを踏まえて、基準となる金額を設定するものです。
この目安をもとに、各都道府県ごとに設置された地方最低賃金審議会が、それぞれの地域事情を考慮して最終的な金額を決定します。地域の企業の支払い能力や生活コスト、他の労働者の賃金などが審議の対象となります。
つまり、国が一方的に金額を決めるのではなく、各地域の意見や状況が反映されたうえで、最終的な最低賃金が決定されるという仕組みになっているのです。
決定プロセスとスケジュール
地域別最低賃金の見直しは、毎年同じような流れで進みます。おおまかには以下のようなステップで構成されています。

引上げの目安提示と調整
6月下旬から7月にかけて、中央最低賃金審議会が「目安額」を公表します。この際、都道府県を複数のランクに分け、それぞれに適した引き上げ額の目安を提示します。
この目安はあくまで参考値であり、各地の事情に応じて上下することもあります。たとえば、景気が回復している都市部では目安以上に引き上げられることもあれば、経済的に厳しい地域では目安以下にとどまることもあります。
地域の実情に基づいた審議の流れ
目安の提示を受け、地方最低賃金審議会が7月から8月にかけて審議を行います。ここでは、公益代表・労働者代表・使用者代表の三者が参加し、地域の経済状況や労働市場、企業の意見などをもとに議論を重ねます。
審議が終了すると、地方労働局長が正式に最低賃金を決定し、公示します。多くの地域では、10月1日前後に新しい最低賃金が施行されるのが一般的です。
最低賃金引き上げが中小企業に与える影響
人件費の増加と経営リスク
最低賃金が引き上げられると、まず直面するのが「人件費の増加」です。特にアルバイトやパートを多く雇用している中小企業では、時給が上がるたびに全体の人件費が大きく膨らみます。売上が横ばいまたは減少傾向にある場合、この負担は経営にとって深刻なダメージとなりかねません。
利益率の低い業種では、賃上げ分を価格に転嫁することが難しく、結果として利益が削られたり、経営自体の見直しを迫られることもあります。とくに地方の小規模事業者や家族経営の店舗では、この影響がより大きく現れやすい傾向があります。
雇用維持・人材確保への影響
最低賃金の上昇は、労働者にとっては賃金の底上げにつながる一方、雇用主側から見ると人件費の圧縮が必要になる場面も出てきます。その結果、非正規労働者のシフト削減や、採用の見送りなどが起こることがあります。
また、他社も一斉に賃上げを行うことで、地域内での人材確保が一層難しくなるケースもあります。賃金競争が起こると、中小企業は大手企業に比べて条件面で劣り、優秀な人材の確保や定着が困難になるリスクがあります。
こうした課題を回避するためには、単に賃金を上げるだけでなく、働きやすさや柔軟な勤務体制といった「総合的な雇用環境」の整備が求められます。
支払い能力を超える場合の対応策
最低賃金を守ることは法律上の義務ですが、経営体力が限界に達している企業にとっては現実的に難しい場合もあります。こうしたときには、まずコスト構造の見直しを行い、無駄な経費の削減や業務効率化による内部改善を図る必要があります。
それでも難しい場合には、国や自治体の支援制度を活用することも一つの方法です。たとえば、厚生労働省が提供している「業務改善助成金」などは、一定の条件を満たせば賃上げにかかる設備投資費用などを補助してくれます。
経営の持続可能性を保ちつつ、法令を順守するためにも、こうした外部支援の利用を前向きに検討すべきタイミングかもしれません。
地域別最低賃金と上手に向き合うための3つの基本
制度の最新情報を常にチェックする
最低賃金は毎年見直されており、その動向は経営に直結します。まず基本として、中小企業の経営者や人事担当者は、地域の最低賃金改定の情報を定期的に確認する習慣を持つことが大切です。
厚生労働省や労働局の公式サイト、業界団体の発表、商工会議所からの通知などを活用することで、確実に正しい情報をキャッチできます。情報の見落としがあると、知らず知らずのうちに最低賃金を下回る雇用契約をしてしまい、法令違反になるリスクがあるため注意が必要です。
経費構造の見直しと業務効率化
最低賃金の引き上げに備えるためには、日頃からコスト管理を意識した経営が重要です。人件費以外の経費に無駄がないかを洗い出し、可能な限り削減する努力が求められます。
また、業務のムダを省き、生産性を向上させることで、同じ人員でもより高い成果を出せる体制づくりが鍵となります。たとえば、ITツールやクラウドサービスの導入による業務自動化は、費用対効果が高く、現場の負担軽減にもつながります。
効率の良い働き方を実現することで、限られた人件費の中でも従業員の満足度と収益性の両立が可能になります。
社会保険や助成金制度を上手く活用する
最低賃金に対応しながら経営を安定させるためには、利用可能な制度を把握し、積極的に活用する姿勢が求められます。たとえば、従業員の雇用や処遇改善に関連する社会保険料の軽減措置や、各種助成金制度が挙げられます。
特に注目されているのが「業務改善助成金」です。これは、生産性向上を目的とした設備投資を行い、従業員の賃上げを実施する中小企業に対して、費用の一部を補助する制度です。要件に合致すれば、最大600万円までの支給が受けられることもあります。
これらの制度を上手に使うことで、無理のない形で賃上げを実現し、経営の安定につなげることができます。
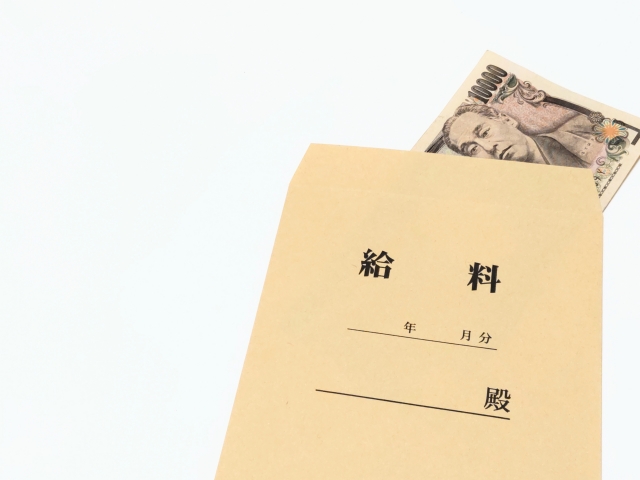
中小企業向け支援制度を活用して経営負担を軽減しよう
業務改善助成金の概要と対象
最低賃金の引き上げに対応するための代表的な支援策として「業務改善助成金」があります。この制度は、中小企業・小規模事業者が賃金の引き上げと同時に生産性を高める取り組みを行った場合、その経費の一部を補助するものです。
対象となるのは、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+50円以内の範囲であること、かつ賃金引き上げとあわせて業務改善を実施する企業です。たとえば、業務用のパソコンやレジの導入、作業工程の見直しなど、業務効率の向上につながる設備投資が補助の対象となります。
対象となる取り組み内容
助成の対象となる取り組みには、以下のような内容が含まれます。
- 作業時間の短縮や負担軽減につながる機器の導入
- 業務フローの見直しや、マニュアル整備による効率化
- ITシステムの導入による管理業務の簡略化
これらの取り組みは、賃上げだけでなく事業全体の改善にも役立つため、経営強化にもつながります。
支給額と申請手続きのポイント
助成額は、賃上げ人数や投資金額、引き上げ幅によって異なり、1事業所あたり最大600万円が支給される場合もあります。申請には、事業実施計画や賃金台帳、見積書などの書類が必要となり、事前の準備が重要です。
手続きは都道府県の労働局またはハローワークが窓口となります。申請受付期間には限りがあるため、情報を早めに収集し、スケジュールに余裕を持って進めることが成功のカギです。
👇業務改善助成金について詳しくはこちら👇
https://emio.jp/news/2025年度対応|業務改善助成金の最新変更点と対策5/
地域によって使える独自支援制度の例
国の制度だけでなく、自治体独自で実施している支援策も見逃せません。たとえば、東京都では「業務改善促進補助金」が設けられており、国の助成金と併用して活用することが可能です。
また、一部の市区町村では、最低賃金引き上げに伴う緊急支援金や雇用安定化補助制度を設けていることもあります。これらの制度は時期によって変動するため、商工会議所や市役所の窓口でこまめに確認することが大切です。
経営相談窓口や専門家の活用も有効
助成金や補助金の制度は、手続きが複雑に見えることもありますが、社労士や中小企業診断士などの専門家の力を借りれば、スムーズに申請を進めることができます。
また、商工会議所や中小企業支援センターなどの公的機関では、無料で相談に応じてくれる窓口も整備されています。自社の状況に合った支援策を探し、申請まで伴走してくれるサービスを活用すれば、より確実に助成金を活かすことができるでしょう。
まとめ:地域別最低賃金を正しく理解し、経営の備えを
地域別最低賃金は、すべての事業者と労働者にとって無関係ではいられない制度です。特に中小企業にとっては、人件費の基準となるため、経営に直接的な影響を与える要素でもあります。制度の趣旨を正しく理解し、毎年の改定情報を見逃さないことが、トラブルを防ぎ、安定した経営を支える第一歩となります。
最低賃金が上がることで経営に不安を感じる場合もあるかもしれませんが、業務の効率化や支援制度の活用など、対応策は決して少なくありません。事前に備えておくことで、急な改定にも柔軟に対応することが可能になります。
本記事で紹介した内容を参考に、自社に合った対策を講じることで、法令を守りながら、健全な事業運営と従業員の安心を両立できる体制づくりを進めていきましょう。



