柔道整復師・鍼灸師の業務委託とは?制度・仕組みをわかりやすく解説
ブログ監修者

プランナー
棚橋 和宏
(たなはし かずひろ)
【保有資格:医療経営士3級】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。
私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。
「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。
補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
Contents
柔道整復師・鍼灸師の業務委託とは?定義と基本の仕組み

業務委託とは?
接骨院・鍼灸院の運営で人手確保が難しくなるなか、「柔道整復師・鍼灸師の業務委託とは?」という観点は、多くの経営者が押さえておきたい点です。業務委託とは、雇用契約を結ばず、対等な立場で外部の施術者に特定の業務を任せる契約形態を指します。院側は必要な業務内容や品質水準、報酬の算定方法を取り決め、受託者はその合意に沿って施術を提供します。勤務時間や働き方は雇用より柔軟で、繁忙期の稼働調整や専門メニューの拡充に活用しやすい仕組みといえるでしょう。ポイントは、契約書で業務範囲と成果、対価、守秘義務などを明確にし、実態が雇用にならないよう運用することです。これにより、コストとリスクを見通しやすくしつつ、院の提供価値を高められます。
業務委託の基本的な考え方
業務委託の基本は「役務の提供に対して対価を支払う」ことにあります。院側は施術というサービスの提供を委ね、受託者は合意した範囲で結果を出す責任を負います。ここで重要なのは、日々の細かな働き方まで院が指示しないことです。勤務開始・終了の時刻、休憩の取り方、施術の段取りなどを細部まで統制すると、雇用に近い関係へ傾きやすくなります。逆に、求めるアウトカムや品質基準、患者対応の基本方針といった「成果と水準」を示し、実現の手段は受託者の裁量に委ねると、委託らしい関係を保ちやすくなります。報酬も時間給ではなく、施術売上や提供件数、パッケージ料金など「成果にひもづく」形で設計すると整合的です。こうした考え方を徹底すると、双方にとって納得度の高い協働が実現しやすくなります。
「請負契約」と「委任契約」の違い
実務で使われる業務委託は、大きく「請負」と「委任」に整理できます。請負は、あらかじめ合意した成果を完成させることに重心があります。たとえば、自費の特別プログラムを一定人数に提供し、コース完了まで担当する、といった完了形のゴールを置くイメージです。成果が明確な分、報酬もパッケージ料金や出来高で設計しやすく、完了・検収の基準を契約書に落とし込むと運用が安定します。これに対し、委任は一定期間、専門スキルを用いた役務を提供することに重きを置きます。院内での施術対応や評価、カウンセリング、リハビリ指導など、日々の専門行為を継続して任せる場面に向いています。こちらは期間と役務内容、品質水準を明確にし、対価は売上歩合や時間単価ではなく、原則として成果や提供実績に連動する形式を選ぶと、委託としての整合が取りやすくなります。いずれの場合も、目的・範囲・成果(または水準)・対価・守秘・期間・解除条件を文章化し、実態が雇用へ寄らない運用を徹底することが肝要です。
雇用契約との違いと業務委託の特徴

接骨院・鍼灸院経営者が柔道整復師・鍼灸師を迎える際、雇用契約と業務委託契約の違いを理解しておくことは欠かせません。雇用契約は、勤務時間や仕事内容、指揮命令系統が明確に決まっており、従業員としての立場が保障される一方、社会保険や福利厚生の負担も院側に発生します。これに対し業務委託契約では、委託者と受託者が対等な立場で合意し、施術内容や報酬形態、勤務条件を自由に設定できます。院側にとっては人件費を変動費化しやすく、必要な時期に専門人材を確保できる一方、施術者は働き方の自由度が高まり、自分のペースで仕事を受けられる特徴があります。
指揮命令・勤務時間の自由度
雇用契約の場合、勤務日や勤務時間、業務内容などは院が決め、施術者はその指示に従う義務を負います。業務委託では、契約で定めた成果や役務の範囲は守る必要がありますが、施術を行う時間帯や方法については施術者の裁量に委ねられるのが原則です。たとえば繁忙時間帯に限定した委託や、特定の施術メニューだけを委ねるなど、柔軟な設計が可能です。これにより院側は必要な時期に必要な業務だけを外部の専門家に任せられ、施術者もライフスタイルに合わせた働き方ができます。
社会保険・福利厚生の扱い
雇用契約では、社会保険料や雇用保険料の事業主負担、年次有給休暇などの福利厚生が義務として発生しますが、業務委託契約では原則としてこれらの義務は発生しません。受託者は個人事業主として自ら保険や税務を管理し、経費計上や節税などの工夫が可能になります。院側にとっては固定費を抑えつつ専門人材を活用できる一方、施術者側には自らの保障を整える自己管理力が求められます。こうした違いを正しく理解したうえで契約形態を選ぶことで、双方にとって納得のいく関係を築きやすくなります。
接骨院・鍼灸院における業務委託の活用事例と期待できる効果

接骨院・鍼灸院では、慢性的な人手不足や施術メニューの多様化に対応するため、柔道整復師・鍼灸師の業務委託活用が広がっています。業務委託は、必要な時期に必要なスキルを持つ施術者を柔軟に迎え入れることができ、経営の安定とサービスの質の向上を両立させる仕組みです。たとえば、保険適用外の自費施術メニューや専門的なリハビリプログラムを期間限定で導入する場合、常勤スタッフを採用するよりも業務委託の方がリスクが低くスピーディーに実現できます。さらに、繁忙期やイベント時だけ増員するなど、需要変動に合わせた運営が可能になり、固定費の抑制にもつながります。
人手不足解消・専門人材確保の手段として
人材不足が課題となる院にとって、業務委託は大きな助けになります。常勤スタッフの採用には時間とコストがかかり、社会保険や教育研修といった負担も伴いますが、業務委託なら必要なスキルを持つ施術者を短期間で確保できます。施術者側も自分の得意分野を活かした契約を選べるため、双方にとって効率的です。特に専門技術や特定領域に強みを持つ施術者をスポット的に活用できるのは大きな魅力で、院のサービス差別化にも役立ちます。
コスト最適化と柔軟な運営
業務委託を活用すると、人件費が固定費から変動費に近づき、経営の柔軟性が高まります。繁忙期には複数の施術者を委託し、閑散期には必要な人数に絞ることで、稼働とコストのバランスを取りやすくなります。さらに、自費診療や季節イベントなど新しい施術プランを試験導入する際にも、業務委託を通じて専門スキルを持つ施術者を期間限定で呼ぶことで、リスクを抑えて新メニューを展開できます。このように、業務委託は単なる人材補充にとどまらず、経営の戦略的なツールとして活用できるのです。
業務委託契約書に盛り込むべき必須項目(施術内容・報酬・期間など)
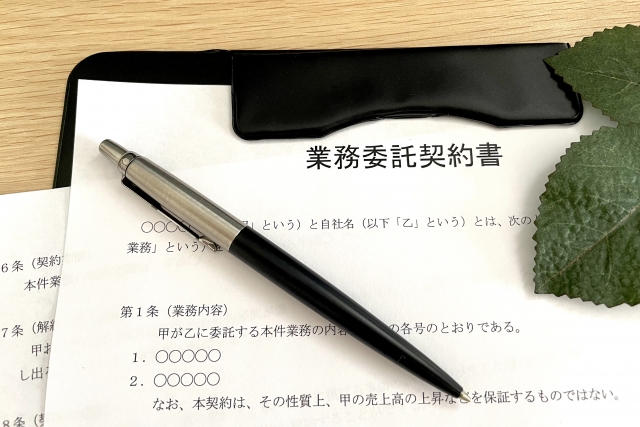
接骨院・鍼灸院が柔道整復師・鍼灸師と業務委託契約を結ぶ際は、契約書の内容を明確にすることが不可欠です。契約の目的や施術の範囲、報酬の形態や支払い方法、業務提供場所や契約期間、秘密保持や個人情報の扱い、契約解除の条件などを細かく定めておくことで、トラブルの防止と業務品質の確保につながります。口頭での合意や曖昧な記載では、後から認識の違いが発生しやすいため、書面で双方が確認できる形にすることが重要です。
契約の目的と業務範囲
契約書には、どのような施術を委託するのか、その目的をはっきりと記載します。たとえば「接骨院内での柔道整復施術業務」や「自費リハビリプログラムの施術提供」など、業務の範囲を具体的に書くことで、受託者の責任範囲が明確になります。また、施術時間や患者対応、使用機器など必要な条件も合わせて示すと、業務の質が一定に保たれます。
報酬形態と支払い条件
報酬は歩合制か固定制か、あるいはその組み合わせかを決め、計算方法や支払いのタイミングも記載します。たとえば「施術売上の50%を月末締め翌月末払い」といった形です。売上の定義やキャンセル時の取り扱いなども事前に決めておくことで、計算方法を巡るトラブルを避けられます。報酬体系を透明にすることは、施術者のモチベーション維持にもつながります。
契約期間・解除条件・秘密保持
契約の有効期間や更新条件、契約解除の方法も重要なポイントです。どのような場合に解除できるのか、通知期間はどれくらいかなどを明記しておくと、急なトラブルにも対応しやすくなります。また、施術中に知り得た患者の個人情報や院内情報は守秘義務の対象とし、情報管理の責任範囲を取り決めることで、信頼関係を保ちながら業務を進めることができます。こうした条項を契約書に盛り込むことで、双方にとって安心できる業務委託関係を築けるでしょう。
法的リスクと注意点(偽装請負・個人情報保護など)

接骨院・鍼灸院が柔道整復師・鍼灸師と業務委託契約を結ぶ際には、制度の理解だけでなく法的リスクの把握が欠かせません。契約内容や運用の仕方によっては、雇用契約とみなされる「偽装請負」や個人情報の漏洩、下請法違反など、経営者側に大きな責任が生じる可能性があります。正しい知識と適切な管理を行えば、リスクを抑えつつ安全に業務委託を活用できます。
偽装請負・下請法違反リスク
業務委託の形を取りながら、実態としては院が施術者に勤務時間や業務手順を細かく指示している場合、雇用契約と見なされるリスクがあります。これが「偽装請負」であり、発覚すると残業代や社会保険料の遡及負担などが発生する可能性があります。また、下請法の適用対象となる場合には、報酬の一方的な減額や不当な条件の強要が違法行為となり、行政指導や罰則を受けることがあります。契約の枠組みだけでなく、実際の運用が契約内容と一致しているか定期的に確認することが大切です。
情報漏洩対策とコンプライアンス
業務委託では、外部の施術者が患者のカルテや個人情報に触れる場面が多くなります。このため、秘密保持契約を交わすことはもちろん、情報へのアクセス制限や管理体制の整備が不可欠です。患者情報の取り扱い方針を契約書に明記し、受託者に遵守を求めることで、漏洩リスクを最小限に抑えられます。また、個人情報保護法など関連法令への対応状況を定期的に確認することも重要です。こうした取り組みを徹底することで、院の信用を守りながら業務委託を安全に運用できます。
まとめ:柔道整復師・鍼灸師の業務委託を正しく理解し活用するために

ここまで、接骨院・鍼灸院経営者が押さえておくべき「柔道整復師・鍼灸師の業務委託とは?制度・仕組みをわかりやすく解説」というテーマで、制度の基本から雇用契約との違い、活用事例、契約書に盛り込むべき必須項目、そして法的リスクと注意点まで整理しました。業務委託は、雇用契約とは異なり、施術内容や報酬、働き方を柔軟に設定できる仕組みです。正しく理解して運用すれば、人手不足の解消や専門人材の確保、コスト最適化といった多くのメリットが期待できますが、契約内容や運用方法を誤ると、偽装請負や情報漏洩などのリスクが生じます。
経営者にとって重要なのは、制度の特徴を踏まえ、契約内容を明確にし、実態が契約と一致するよう管理することです。そのうえで、必要に応じて専門家の助言を受けながら、自院に合った形で業務委託を活用することが、持続的な経営とサービス品質向上の鍵となります。次回の記事では、委託者側にとってのメリット・デメリットをさらに深掘りし、実践に役立つポイントを紹介していきます。



